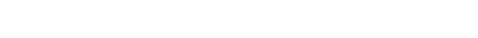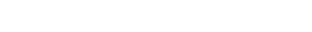防犯カメラで撮影できる範囲はどれくらい?確認方法や注意点を解説

防犯カメラで重要なのが「撮影範囲」です。
今回は、防犯カメラの撮影範囲を確認する方法、撮影範囲の広い防犯カメラの選び方、注意点について解説します。
もくじ
防犯カメラの撮影範囲を確認する方法

防犯カメラの撮影範囲を確認する方法は、以下の通りです。
「画角」を調べる
防犯カメラの撮影範囲を調べるために、まずはレンズごとの「画角」を確認しましょう。
レンズには、大きく分けて以下の3種類があります。
標準レンズ
標準レンズは、画角47度前後、焦点距離は50mm程度で、防犯カメラでは最も代表的なレンズの種類です。
広範囲の撮影には適していませんが、玄関や駐車場など、限定的な場所の監視であれば問題ないでしょう。
望遠レンズ
望遠レンズは、画角が24度前後と狭い代わりに、焦点距離は100mm以上あります。
広範囲の撮影には不向きですが、遠くの対象物もしっかり撮影できるというメリットがあります。
広角レンズ
広角レンズは、画角が63度前後と広く、焦点距離が35mm以下と狭いとのが特徴です。
なかには画角75度前後、焦点距離24mm以下の超広角レンズもあります。
風景撮影から室内での人物撮影まで、幅広く対応できるのがメリットです。
「焦点距離」を調べる
焦点距離とは、ピントを合わせた時のレンズの中心からフィルム面のイメージセンサー(撮像素子)までの距離のことです。
イメージセンサーとは、レンズに入った光を電気信号に変換する役割を持つ半導体で、人間の眼で言えば網膜に相当します。
防犯カメラの撮影範囲は、焦点距離が短いほど広くなり、焦点距離が長いほど狭くなります。
「チルト(垂直画角)」「パン(水平画角)」を調べる
防犯カメラの撮影範囲は、カメラの動作によっても左右されます。
レンズが上下に動くことをチルト(垂直画角)といい、左右に動くことをパン(水平画角)といいます。
いずれかの動作にしか対応していない防犯カメラもありますが、上下左右どちらにも対応するPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラもあります。
PTZカメラなら、レンズが縦にも横にも動くため、撮影範囲が広くなります。
「撮影範囲」を計算する
撮影したいものまでの距離と水平画角、垂直画角がわかっていれば、三角関数の公式を使って撮影範囲を計算することができます。
まずは以下の計算式で、tanθと撮影可能範囲の半分(bc)を算出します。
-
tanθ(画角の半分)=撮影可能範囲の半分(bc)/撮影対象までの距離(ac)
例えば、水平画角が90度の場合、tanθは45度です。
tanθは関数電卓で「tan」を使用すると算出されます。今回は、関数電卓で「tan+45」と入力して、「1」という数字がでました。
つまり、
1=撮影可能範囲の半分(bc)/7m
となり、bcは7mであることが分かります。
さらに、以下の式に当てはめて撮影範囲を計算してみましょう。
-
撮影範囲 =tanθ×撮影可能範囲の半分(bc)×2
撮影範囲は「1×7m×2」で14mとなります。
撮影範囲の広い防犯カメラを選ぶポイント

続いては、撮影範囲の広い防犯カメラを選ぶポイントを解説します。
目的を明確にする
まずは、防犯カメラの設置目的を明確にします。
例えば、駐車場や倉庫、店舗などで人の動きを大まかに監視するなら、広範囲の撮影ができる広角レンズが適しています。
一方、駐車場の車上荒らしやコンビニ強盗など、不審者対策として防犯カメラを設置する場合は、犯罪者の顔までしっかりと撮影できる望遠レンズの防犯カメラがおすすめです。
設置場所に合わせる
次に、防犯カメラの設置場所を考えてみましょう。
例えば、コンビニの出入り口などに設置する場合、見た目にインパクトが少なく、邪魔にならないコンパクトなタイプの防犯カメラがおすすめです。
また、駐車場などの屋外に設置する場合は、防水機能が備わった屋外用の防犯カメラを選ぶ必要があるでしょう。雨や風によるダメージで故障してしまう可能性があるため、注意が必要です。
屋外設置可能な防犯カメラのなかには、赤外線機能付きで夜間撮影に対応したものもあり、24時間監視が必要なケースに適しています。
防犯カメラの撮影範囲に関する注意点
続いては、防犯カメラの撮影範囲に関する注意点を説明します。
赤外線での撮影範囲
暗闇でも撮影が可能な赤外線カメラは、赤外線の光が届く範囲しか撮影できません。
つまり、赤外線の照射距離がそのまま撮影可能範囲となり、昼間の撮影範囲とは異なるケースも多いので注意が必要です。
一般的な赤外線カメラの撮影範囲は15m程度ですが、屋外で撮影する防犯カメラであれば、20m~30m程度のものを選ぶと良いでしょう。
死角をつくらない
せっかく防犯カメラを設置しても、死角が多いと防犯効果が薄れてしまいます。
特に死角になりやすいと言われているのが、防犯カメラの真下です。
死角を作りたくないという方におすすめなのが、縦にも横にも動くPTZカメラの活用です。
PTZカメラなら、真下も死角になりません。
また、同じ場所に複数台の防犯カメラを設置するのも効果的な方法です。
防犯カメラの死角をなくす方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
「防犯カメラ・監視カメラの死角をなくす方法はある?選び方や設置場所のコツ」
プライバシーへの配慮
個人を特定できるほど鮮明な映像を記録できる防犯カメラを設置する場合は、プライバシーへの配慮が必要です。
特に、不特定多数の人が通行する屋外に防犯カメラを設置するときは、「防犯カメラを設置している旨」をしっかりと明示するようにしましょう。
大きなトラブルにつながらないよう、撮影データについても慎重に取り扱う必要があります。自治体ごとに「防犯カメラ設置のガイドライン」が策定されているので、事前に確認しておくと良いでしょう。
撮影範囲が広い防犯カメラを設置しよう

今回は、防犯カメラの撮影範囲や、撮影範囲の広い防犯カメラの選び方について紹介しました。
建設現場や工事現場はもちろん、駐車場、倉庫、店舗などの防犯対策には、撮影範囲が広い防犯カメラを活用しましょう。
また、死角をできるだけ少なくするのも大切なポイントです。
PTZカメラが内蔵されたものを使用することや、1箇所に複数台設置することを検討してみてはいかがでしょうか。
カンタン監視カメラのG-camは、360°以上監視可能なPTZカメラを内蔵した防犯カメラです。
最大50mの赤外線照射モードも搭載しており、夜間もしっかり撮影することができます。光学5倍ズーム機能付きで、撮影対象が離れていても問題ありません。
初期費用0円のレンタルカメラなので、月額費用のみで設置ができ、複数台使用したい方にもぴったりです。
カンタン監視カメラG-camについてより詳しい情報を知りたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。