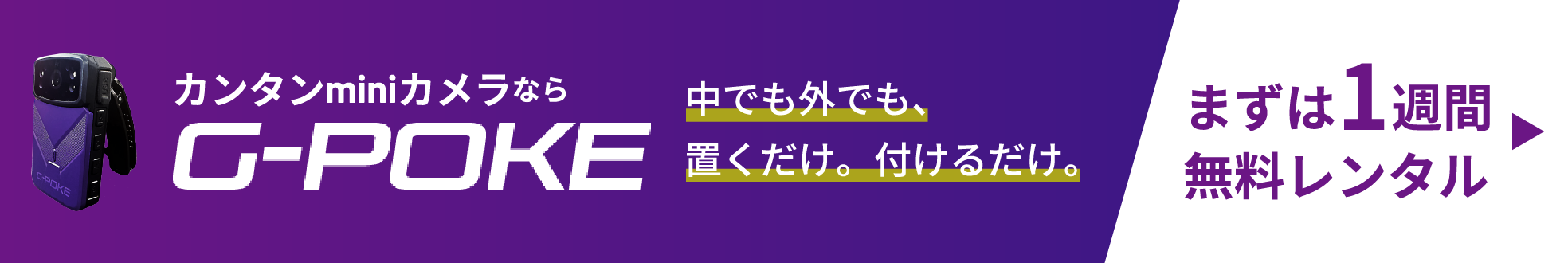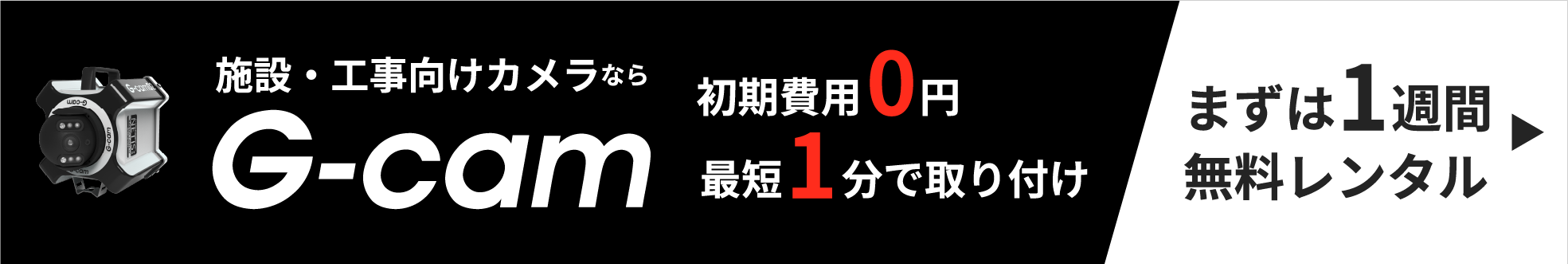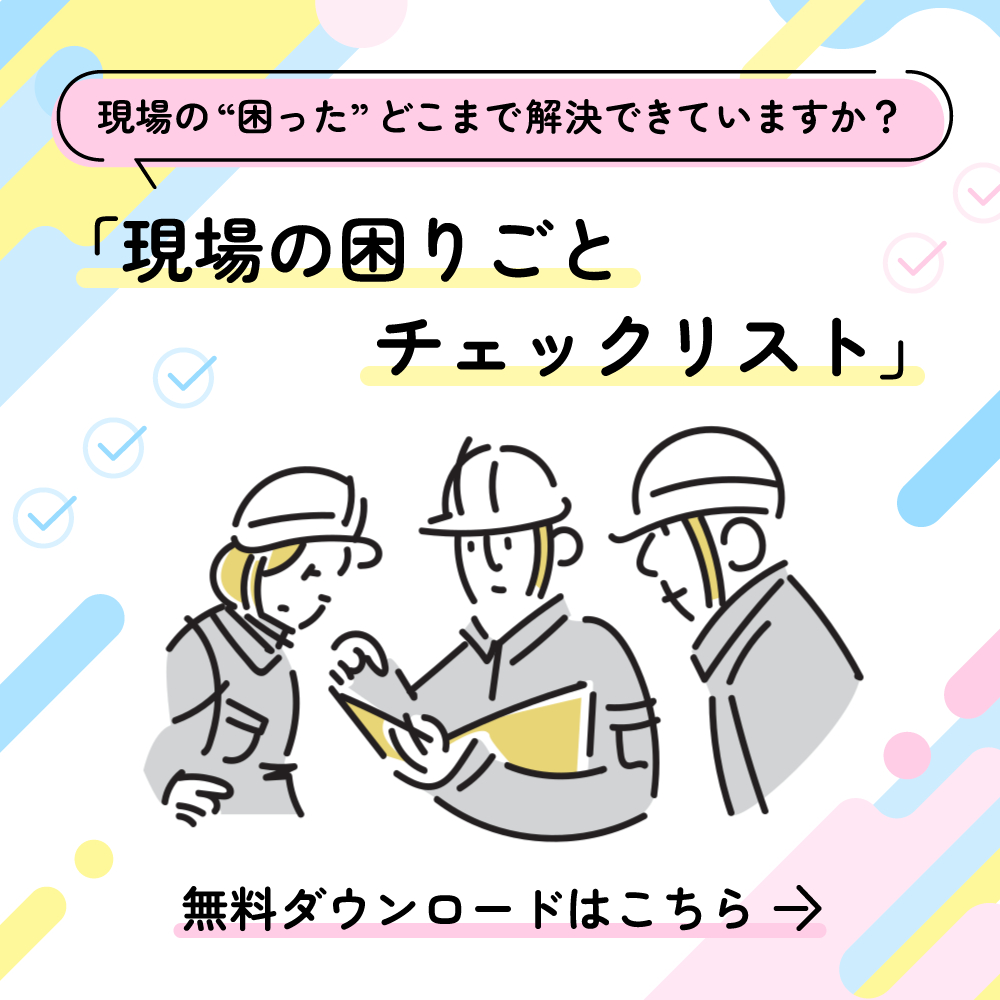不安全行動とは、安全に対する配慮が欠けた行動や、危険と知りながらとってしまう行動のことです。厚生労働省のデータによると、労働災害全体の96%以上に不安全行動が関わっています。「気をつけろ」「注意しろ」という声かけだけでは、本質的な改善は望めません。
そこで本記事では、厚生労働省が示すアプローチをもとに、現場での不安全行動をなくす対策を中心に紹介します。現場を「見える化」するツールの活用法も交えて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
なお、下記の記事では不安全行動の定義から実際に起こった事例、現場で使えるチェックリストまでを体系的にまとめました。「そもそもなぜ不安全行動をしてしまうのか」という背景から知りたい方は、まず下記の記事をご覧ください。
不安全行動をなくすための4つの対策

不安全行動を根本的に減らすには、作業員の意識に頼らない仕組みと習慣の見直しが不可欠です。
本章では、厚生労働省が推奨する方法をもとに、4つの視点から対策を紹介します。
どれかに偏ることなく、4つの視点での対策をバランスよく実施することがポイントです。
対策1.人間を対象とした対策(安全教育・意識啓発)
不安全行動の根本には、危険に対する認識不足や油断、慣れといった人間の意識の問題があります。
その意識の問題にアプローチする対策が、安全教育と意識啓発です。
同じ会社の作業員が体験した事例をもとにした安全教育や危険意識の啓発は、「自分の身にも起こるかもしれない」と感じやすく、自分事としてとらえやすくなります。
項目ごとの具体例を下記の表にまとめましたので、対策を練る際の参考にしてください。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| KYT(危険予知訓練) | ・朝礼時に当日の作業に関する危険箇所を現場写真で確認し合う ・チームディスカッションを行い、全員の気付きを共有する ・危険ポイントを作業図にマーキングし、現場に掲示する |
| OJT(現場教育) | ・新人の横に熟練作業員が付き、注意点を伝えながら実演指導する ・1つずつ手順を確認しながらその場で予測できる危険性を説明する ・作業後すぐに振り返り時間を設け、記憶が鮮明なうちに改善点をチームで整理する |
| ヒヤリハット事例の共有 | ・週1回のミーティングで1件ずつ事例の対策を話し合う ・社内のシステムなどで事例を閲覧可能にし、対策案を受け付ける ・映像付きの社内事例集を作成し、教育資料として定期的に使用する |
| 安全ポスターや標語の掲示 | ・現場スタッフが過去の経験から学んだ教訓を一言メッセージにして掲示する ・写真付きのオリジナルポスターを、休憩所や更衣室に掲示する ・作業動画へのQRコードを添付したポスターを掲示する |
作業者の危険に対する感受性を高め、正しい行動をうながすには、文字や静止画では伝わりにくい複雑な手順や危険動作を、動画で視覚的に示すことが有効です。
そこでおすすめしたいのが、作業者の視点で手順や行動をリアルに記録できる株式会社MIYOSHIのカンタンminiカメラ「G-POKE(ジーポケ)」です。胸やヘルメットに装着してハンズフリー撮影ができるため、臨場感あふれる現場の映像を手軽に残すことができます。

スピーカー機能と最大10倍のデジタルズームを搭載しており、経験の浅い作業員の動きをベテランが遠隔から確認し、声かけ・指導することが可能です。最大8時間の連続稼働で1日の作業全体を通して記録できるため、安全教育の資料作りや手順書の動画作成の際にも役立ちます。
初期費用0円、月額9,800円からレンタル可能な「G-POKE」の詳細は、下記のバナーをクリックのうえ資料をダウンロードしてご覧ください。
\ 小さな不安全行動も見逃さない! /
対策2.管理を対象とした対策(安全管理体制の整備)
現場の安全は、作業者個人の注意力や責任感だけに頼って維持できるものではありません。組織としての安全管理体制が整備されてこそ、持続的な安全対策につながります。
ここでは、安全管理体制を強化するために重要な「仕組み化」と「現場の習慣の見直し」に着目し、実際の取り組み例を項目別に整理しました。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| リスクアセスメントの実施 | ・現場で録画した作業を振り返り、具体的な危険箇所を洗い出す ・各作業工程に点数をつけて、リスクレベルを可視化する ・月ごとの振り返りミーティングでリスク評価と改善状況を共有する |
| 作業手順書の見直しと整備 | ・手順書の内容を動画と連動させ、視覚的に理解しやすくする ・現場からのフィードバックをもとに、実態に合った記述に修正する ・外国人作業者向けに、多言語対応やピクトグラム(視覚的な記号や絵文字)付きの手順書を用意する ▼ピクトグラムの例(出典:千葉労働局 災防ピクトグラム) |
| 安全衛生委員会の定期開催 | ・毎月の定例会議で、直近の事故やヒヤリハットを映像や図解で振り返り、再発防止策を話し合う ・各現場からの代表者による現場主導の改善提案を奨励する ・現場巡視で気付いた点や作業員から寄せられた「やりづらい」などの声を拾い上げ、安全上の課題として共有する |
ちなみに、作業工程を撮影できる監視カメラを定点設置すれば、巡回では把握しづらい不安全行動や動線の乱れを24時間確認できます。映像によって作業のクセや危険な動線が客観的に可視化され、手順書だけでは見落としがちなリスクの発見につながります。
映像を通じて現場全員が同じ危険認識を共有し、管理面での対策の必要性も納得しやすくなる点でも、監視カメラの活用はおすすめです。
対策3.作業方法を対象とした対策(安全な作業方法の確立)
現場の安全と品質を確保するには、作業員の注意力や経験に頼らない「仕組み化された作業方法」を整備することが欠かせません。作業内容を明確に定め、誰が実施しても同じように進められる状態をつくることで、ミスや事故のリスクを低減できます。
作業標準や確認手順の明文化、視覚的なサポートの導入など、下記を参考に対策を進めましょう。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 作業手順の標準化 | ・熟練作業員の手順を動画で記録し、標準作業として設定する ・手順をフローチャート形式で記載し、掲示板に貼る ・改訂履歴を明記した手順書で、更新内容が一目でわかるようにする |
| チェックリストの導入 | ・作業前後に確認するポイントを時系列で整理したリストを配布する ・現場ごとに必要な項目をカスタマイズし、作業員のスマートフォンですぐに確認できるようにする ・チェックの記入状況をリーダーが週次で確認しフィードバックする >>チェックリストの例はこちら |
| 指差呼称の徹底 | ・声かけも含めた動作をマニュアル化する ・指差し動作を動画で撮影し教育素材として活用する ・声出し確認を推進するキャンペーンを期間限定で実施する |
標準化やチェックリストは一度作って終わりではなく、現場の変化や改善提案に応じて更新していくことが大切です。作業者の声を取り入れながら、より実用的で現場に根付いた作業ルールを育てていきましょう。
対策4.作業環境・設備を対象とした対策(物理的対策)
いかに作業員が注意していても、物理的な環境が整備されていなければ事故を防ぐことはできません。
通路が狭い・照明が暗い・保護具の数が足りないなど、小さな問題が不安全行動の引き金になることもあります。
不十分な環境整備によるリスクを見逃さないためのチェック項目を、下記にまとめました。現場で不足している点や、さらに改善できる点がないか、チェックしてみてください。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 動線の確保 | ・フロアに色別のラインテープを貼り、作業・通行・退避ルートを分離する ・看板や足元サインで一方通行を徹底する ・動線を記した現場マップを掲示し新人にもわかりやすくする |
| 照明の最適化 | ・死角や暗がりをカメラ映像で特定し、追加照明を設置する ・モーションセンサー付きLEDライトを導入し省エネにも対応する ・点検表に照度チェック項目を追加し定期的に改善する |
| 安全装置や保護具の配置と点検 | ・必要な保護具を使用場所ごとに配置し、使用率を記録する ・点検用のQRコードを貼り、点検記録漏れなどの検索や通知がしやすいデジタルで管理する ・装置の作動確認を毎朝の朝礼時にローテーションで実施する |
作業環境や設備の対策においては、必要な保護具の使用率を数値で管理すると効果的です。使用漏れの傾向を把握しやすく、対策の効果測定にもつながります。
危険を未然に排除するには、小さな問題でも見過ごさずに改善する仕組みづくりがポイントです。
不安全行動の対策を導入する際の5つのステップ

本章では、不安全行動の対策を現場で取り組みやすい形に落とし込むためのステップを5つに分けてご紹介します。
「まず何から始めればいいのか」と迷ったときの参考にしてみてください。
ステップ1.現場の不安全行動を可視化する
現場でどのような不安全行動が起きているのかを把握することが、最初のステップです。
例えば、「つい脚立を使わず高所に手を伸ばしてしまう」「安全靴を履かずに作業している」など、見過ごされがちな行動も少なくありません。
| 【可視化の例】 ・カメラを使って作業を録画し、無意識の不安全行動を可視化する ・定点カメラ映像から、立入禁止エリアへの侵入や動線の乱れを発見する ・定期的に映像を振り返り、チェックリストと照らし合わせて分析する |
まずは監視カメラやチェックリストを活用し、複数の目で不安全行動を洗い出しましょう。
ステップ2.チームで課題を共有する
不安全行動は、個人の問題ではなく現場全体で取り組むべき課題です。可視化した結果をチーム内で共有し、現場全体で改善に取り組みましょう。
| 【共有の例】 ・ヒヤリハットをTeamsやSlackなどの共有ツールに記録し、全員が閲覧・コメントできるようにする ・週1回のミーティングで映像を一緒に見ながら話し合う ・安全掲示板に「今週の気付きコーナー」を設けて自由に書き込めるようにする |
ステップ3.対策の優先順位を決める
課題を共有した後は、どの対策から着手すべきか優先順位を決めます。
| 【優先順位を決める際のポイント】 ・リスクの高さで決める→高所作業や重量物の取り扱いのように、事故時の影響が大きい工程など ・改善のしやすさで選ぶ→既存マニュアル・手順書を修正するだけで改善できる箇所など ・発生頻度で選ぶ→月に1件以上ヒヤリハットが起きている箇所など |
リスクが高いものはどれか、改善しやすいものはどれかの視点から選定してみましょう。
ステップ4.小さく試して効果を測る
優先順位が決まったら、まずは下記のように小さく試して効果を確認します。
| 【実践と効果の測り方の例】 (具体例1) ・新人作業員に、動画教育とOJTを組み合わせた安全指導を試行する ・新人作業員に同じ作業をしてもらい、教育担当者が確認する ・指導前後での作業ミス件数比較、理解度テスト、教育担当者によるチェックシート記録などで効果を測定する (具体例2) ・仕上げ作業の1工程に限定してチェックリストを使用し、作業ミスが減るか検証する ・該当工程のやり直し件数や指摘数などで、作業の正確性が向上したか確認する ・作業者がどの程度チェックリストを記入・提出しているかを集計し、記入の習慣が現場に根づいてきているかを測定する |
いきなり工程全体に影響がある対策を取り入れると、現場の作業員に大きな負担がかかってしまいます。現場の意見も取り入れて実践することが、現場で不安全行動対策を浸透させるコツです。
ステップ5.成果を確認し横展開する
効果が確認できたら、他の現場や作業工程にも横展開していきます。
| 【成果の確認と横展開のやり方の例】 ・KPIとして、ヒヤリハット件数・指摘数・教育参加率などを毎月記録する ・成果の出た教育方法やチェックリストを別部署にも共有する ・成功事例を動画マニュアル化し、他チームの朝礼やミーティングで活用する |
数字で成果を見える化し成功事例を蓄積することで、継続的な安全文化が育っていきます。
監視カメラが不安全行動削減に貢献した事例

最後に監視カメラの導入により、安全管理に加え業務効率化も実現させた企業の事例を紹介します。

株式会社東京ドーム様では、2020年の大規模なイベントをきっかけに会場内やバックヤードでの安全管理に、株式会社MIYOSHIが提供するカンタン監視カメラ「G-cam」を導入されました。
| 導入前の課題 | ・約300の出店者様の膨大な荷物管理が必要だった ・バックヤードで、荷崩れなどの危険を防ぐ安全管理が求められていた ・盗難防止のため、鍵の管理にスタッフが必要となり会場巡回の人手が不足していた ・広い会場では、目視での管理に限界があった ・多くの人員をかけない「警備の効率化」が求められていた |
|---|---|
| 導入の効果 | ・カメラ映像で危険な荷物の高積み発生がわかり、必要なときのみの声かけで少ない人員でも安全に運営できた ・バックヤードにカメラがあることで、危険な荷積みの抑止力になった ・カメラ映像で会場の動線を把握でき、適切なタイミングで人員配置できた ・会場を俯瞰で見られ、少ないながらも効果的な人員配置で効率的に警備できた |
安全管理や業務効率化だけでなく、不安全行動の抑止力にも「G-cam」が役に立ったそうです。株式会社東京ドーム様の詳しい内容は、下記の記事からお読みいただけます。
>>>G-cam・G-POKEの導入が、東京ドーム大規模イベントの警備効率化に貢献した事例
不安全行動をなくし安心安全な現場を目指そう

不安全行動をなくすには、「人」「管理」「作業方法」「環境」の4つの視点でバランスの取れた対策が求められます。そして対策に役立つのが、現場の実態を正確に見える化するツールの活用です。
株式会社MIYOSHIのカンタンminiカメラ「G-POKE」は、重さわずか165gで装着の負担が少なく、作業の邪魔になりにくいのが特長です。作業者の視点でリアルな映像を記録できるため、不安全行動が発生しやすい具体的な場面を特定したり、安全な作業手順の教育資料として活用したりするのに役立ちます。また、定点カメラとして活用できる簡単監視カメラ「G-cam」は、360°対応で真下・真後ろまで監視できるため、死角になりやすい場所での不安全行動や危険な動線を「見える化」します。

初期費用0円、月額9,800円からレンタルでき、1週間のお試しも可能な「G-POKE」「G-cam」の詳細は、下記のボタンをクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。
\ 無意識な不安全行動を「見える化」! /