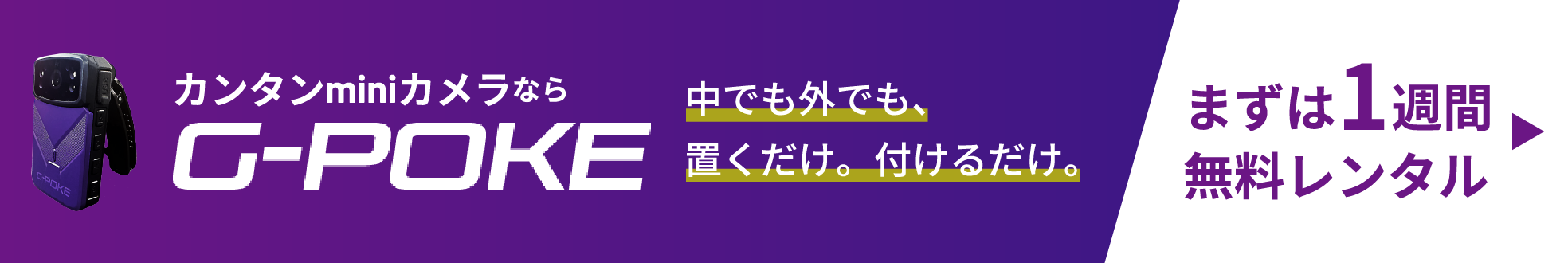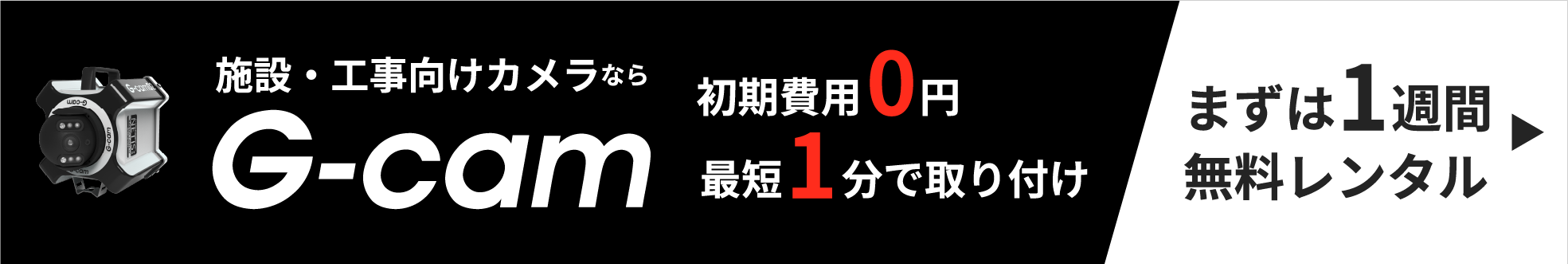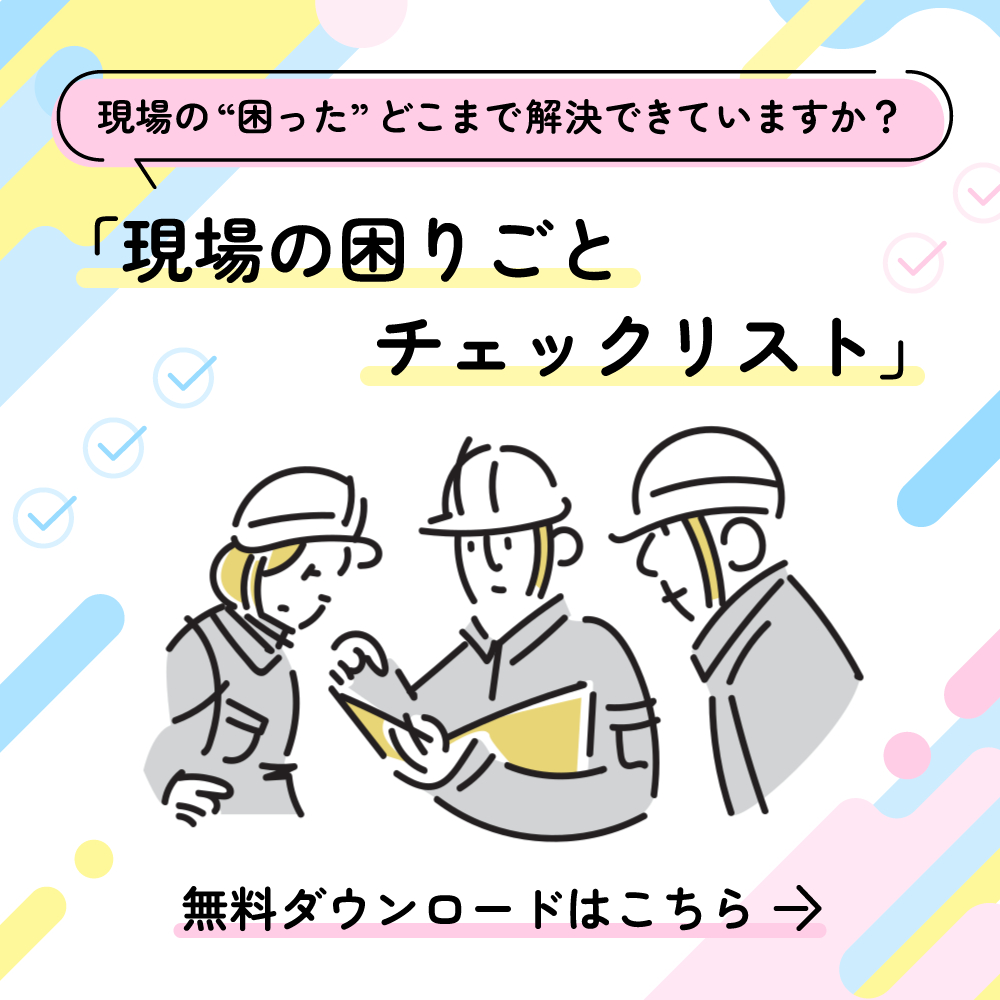雑踏警備とは、多くの人が集まるイベントや行事で事故や混乱を防ぎ、安全を確保するために欠かせない警備業務です。わずかなきっかけで転倒や将棋倒しなどの重大事故が起こることもあり、専門的な知識を持つ警備員の配置や計画的な警備体制が求められています。
本記事では、雑踏警備の必要性や警備に必要な検定・求められる役割・課題・対策を紹介します。
なお、現場の警備力を強化するなら、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam(ジーカム)」がおすすめです。
初期費用・往復送料0円で1ヵ月9,800円から利用できるため、短期イベントや一時的な監視が必要な雑踏警備に適している「G-cam」については、下記から気軽に資料をダウンロードしてみてください。
\ 営業日15時までのご注文で即日発送! /
目次
雑踏警備とは

雑踏警備とは、不特定多数の人が集まる場所で事故や事件の発生を警戒し、防止するための警備業務です。総務省消防庁によると、雑踏警備は下記のように定義されています。
雑踏警備とは、祭礼、花火大会、その他の行事等の開催により、特定の場所に不特定多数の人が一時的に集まることにより、事故若しくは混乱等が発生するおそれがある場合において、部隊活動により事故、交通の規制等の諸活動を行うもの。
警備の対象は、雑踏による事故が起こるおそれのない小規模なものを除き、下記のように「多くの人が集まる催し」と位置付けられています。
|
なお下記の記事では、雑踏警備を含むイベント警備の基礎から運営効率を高めるコツまで網羅的に解説しているのでご覧ください。
雑踏警備の必要性
雑踏警備が強く求められるようになった背景には、過去に発生した重大な群衆事故の存在があります。
【明石花火大会歩道橋事故(2001年)】
|
この事故をきっかけに、兵庫県警は2002年、事故の再発防止のために「雑踏警備の手引き」を作成し、群衆や雑踏に関する安全対策や警備の重要性を説明しています。内容の一例を下記にまとめました。
|
また、この事故から4年後の2005年(平成17年)には、警備業法と国家公安委員会規則が改正され、新たに「雑踏警備」というカテゴリが警備業務検定に追加されたという背景があります。
参考:警備員等の検定等に関する規則 | e-Gov 法令検索
イベントの責任者は、すべての雑踏警備業務について検定合格警備員を配置することも定められています。
雑踏の3つの特色
どのくらいの人数からを「雑踏」と定義されるのかは定められていません。ここでは、兵庫県警察の資料をもとにした、雑踏の特色をまとめました。
| 不特定多数の人の集合 | ・年齢・性別・思想などさまざま ・集団としての性格も複雑 ・秩序づける組織も権威も存在しない |
|---|---|
| 個々人の進行・慰安・娯楽などを目的とした集団 | 労働運動・政治運動など同一の主張を掲げてその貫徹を図る集団は雑踏とは異なる |
| 人の集合が事前に予測可能 | ・雑踏の多くは、恒例的・年中的な行事に関連して早くから予測ができる ・インターネットを通じた呼びかけによる突発的な集合事案が発生することも考えられる |
雑踏警備業務検定とは
雑踏警備業務検定とは、雑踏警備の専門家であることを証明する国家資格です。多数の人が集まる場所での事故や混乱を防止するために、必要な知識と能力を測る検定です。
検定の主な概要を、下記にまとめました。
| 雑踏警備業務検定2級 | 取得に条件は不要。申し込みは下記まで 雑踏警備業務|一般社団法人 警備員特別講習事業センター |
|---|---|
| 雑踏警備業務検定1級 | 2級を取得してから1年以上の業務経験が必要 |
| 資格の目的 | 雑踏における事故防止、安全なイベント運営 |
| 試験内容 | ・学科試験:法令、雑踏警備に関する知識 ・実技試験:負傷者の搬送、応急処置、護身術など 詳細は下記を参照 雑踏警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準 |
前述したように、警備業法により雑踏警備業務を行う場所には、検定合格警備員の配置が義務付けられています。資格を持つことで、専門的な知識と技能を有することが証明され、警備業務における信頼性が高まります。
雑踏警備と交通誘導との違い
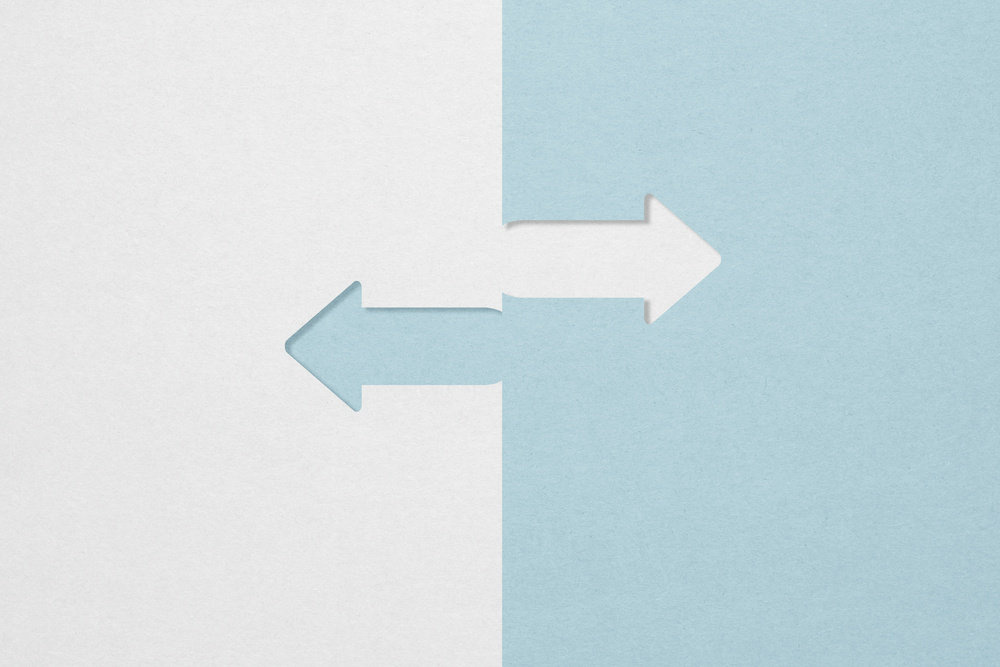
雑踏警備と交通誘導の違いは、大きく「人の誘導に特化しているか、車両を含めた誘導を行うか」です。どちらも警備業法上の2号業務に分類される警備員ですが、業務内容は違いがあります。それぞれの違いを表にまとめました。
| 項目 | 雑踏警備 | 交通誘導 |
|---|---|---|
| 主な現場 | イベント会場・祭り・花火大会・スポーツ大会など大勢が集まる場所 | 道路工事現場・建築現場・駐車場・商業施設周辺 など |
| 主な目的 | ・雑踏事故や混乱の防止 ・安全な人の流れの確保 | ・車両や通行人の安全確保 ・交通の円滑な流れの維持 |
| 主な業務内容 | ・人の流れや分散の誘導 ・不審者や立入禁止区域の監視 ・周辺交通案内 | ・車両・歩行者の誘導 ・交通規制車線コントロール ・駐車場案内 |
参考:雑踏・交通誘導警備員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))
共通点としては、どちらも警察官と違い法的強制力はなく、対象者への任意協力を求める行為にとどまることです。加えて、状況に応じ気分が悪くなった人の保護や、車椅子を利用する人の誘導を行うことも共通しています。
雑踏警備の必要性が高まる4つのシーン

本章では、雑踏警備が必要な代表的なシーンについて紹介します。
シーン1.花火大会で安全を守る
花火大会は、美しい花火を観るために多くの人が集まるイベントです。しかし、下記のような危険性も潜んでいます。
【考えられる危険】
|
そこで、雑踏警備に求められる主な役割は次のとおりです。
【雑踏警備に求められる役割】
|
暗がりでの段差や川沿いの足元にも注意しながら、計画的な警備が必要です。
シーン2.ライブ会場で混雑防止を行う
ライブ会場は、アーティストのパフォーマンスを楽しむために多くのファンが集まる場所ですが、下記のようなリスクも考えられます。
【考えられるリスク】
|
ライブ会場の雑踏警備では、下記のような対応が求められます。
【雑踏警備に求められる役割】
|
混雑する開場前後の行列・グッズ売り場周辺・ライブ後の退場時などは、押し合いや転倒事故が起こりやすいため、スムーズな誘導や適切な整理が大切です。
シーン3.初詣で事故防止を実現する
初詣は、新年を迎えるにあたり、多くの人が神社仏閣に参拝する日本の伝統行事です。場所によっては、短期間に多数の参拝客が訪れるため、下記のようなリスクが考えられます。
【考えられるリスク】
|
初詣での雑踏警備に求められる業務は、下記のとおりです。
【雑踏警備に求められる役割】
|
狭い参道や長い階段付近では人が滞留しやすく、転倒や圧迫事故のリスクが高まるため、流れを途切れさせない誘導や声かけが大切です。
シーン4.スポーツイベントで誘導を担う
スポーツイベントは、多くの観客が試合の展開や選手のプレーに熱狂する場所であり、下記のような注意点があります。
【考えられるリスク】
|
スポーツイベントで雑踏警備に求められる主な役割は、下記のとおりです。
【雑踏警備に求められる役割】
|
試合終了後の一斉退場時や飲食エリア周辺は混雑やトラブルが発生しやすいため、円滑な動線確保と冷静な誘導が欠かせません。
雑踏警備の課題と対策

雑踏警備では、現場での安全確保とスムーズな運営を確保するために、次のような課題が発生しやすくなります。
|
こうした課題を解決に導く手段の一つが、監視カメラを併用することです。
例えば、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」および小型ボディカメラ「G-POKE」は、初期費用・往復送料0円で1ヵ月から利用できるため、短期イベントや一時的な監視が必要な雑踏警備に適しています。
営業日15時までのご注文で即日発送ができ、急な警備強化が必要な場合でも準備の負担軽減が可能です。
「G-cam」が、雑踏警備のサポートとして適している理由を紹介します。
| G-camの特徴 | 雑踏警備に適している理由 |
|---|---|
| 取り付けはたった3ステップ | 現場での設置作業が簡単で、専門知識がなくても短時間で稼働開始できる |
| モバイルSIMと設定済みルーター内蔵で、複雑な設定は不要 | 電源を確保すればすぐに使用開始でき、イベント直前の設置や急な増設にも対応可能 |
| レンズ横回転最大350°縦回転最大90°真下・真後ろまで監視できる | 少ないカメラ台数で広範囲を監視できて経済的 |
| 光学4倍ズームで離れた対象も大きく映し出す | 遠くの不審な動きや混雑状況を詳細に確認でき、トラブル発生時の証拠映像としても役立つ |
| IP66(※)相当の防塵防水機能で全天候に対応 | 雨天や風が強い日でも安定した映像提供が可能で、天候に左右されない警備体制を構築 |
| 株式会社MIYOSHIが提供するソーラーバッテリー「ソラセル」と併用できる | 電源の確保が難しい屋外や駐車場などでも、無日照でも約1週間の稼働が可能 |
(※)IP66……日本産業規格で防塵・防水に関する等級
夜間でも自動で赤外線に切り替わり、鮮明な映像が撮影できる「G-cam」については、下記から資料をダウンロードしてご確認ください。
\横350°・縦90°回転可能なレンズで真下・真後ろまで監視できる! /
また、台風などの激しい雨でも浸水のおそれがない「ソラセル」は下記からチェックしてみてください。
次に紹介する「G-POKE」は、警備員が胸などにつけて使用できる小型ボディカメラです。危険箇所や不審者の情報をその場で共有、映像を添えて即時にチーム内で確認できるため、迅速で的確な対応が実現します。
「G-POKE」の雑踏警備に役立つ特徴は、下記のとおりです。
| G-POKEの特徴 | G-POKEが雑踏警備に適している理由 |
|---|---|
| わずか165gの軽さ | 長時間の使用でも体への負担が少ない |
| インカム機能 |
|
| タッチパネル方式 | スマートフォンなどで馴染みがあるため、幅広い年代の方が使いやすく、教育コストが抑えられる |
| バッテリー・Wi-Fi不要 |
|
| IP67相当の防塵防水機能で全天候に対応 |
|
持ち歩き撮影だけでなく、三脚に固定して定点カメラとしても使用できる「G-POKE」については下記から気軽に資料をダウンロードして、ご確認ください。
\バッテリーやWi-Fiも不要!/
雑踏警備に関してよくある2つのQ&A

最後に、雑踏警備に関してよくある質問に回答します。
気になるものがあれば、チェックしてみてください。
Q1.雑踏警備員に資格は必要ですか?
資格がなくても、雑踏警備で働くことは可能です。
しかし、「すべての雑踏警備業務について、検定合格警備員を配置する必要がある」ことから、「雑踏警備業務検定」を保有していたほうが、警備の現場では優遇されやすいといえます。
また資格を保有していることで、より専門的な知識や技能を持っていることを証明できるため、信頼性の向上にもつながります。雑踏警備業務に従事する場合は、「雑踏警備業務検定」資格の取得を目指すことがおすすめです。
Q2.雑踏警備を依頼するまでの流れは?
一般的な流れを、一覧にまとめたのでチェックしてみてください。
| イベントの概要を整理 | ・開催日時・場所・参加予定人数・イベント内容などの基本情報をまとめる |
|---|---|
| 警備会社の選定 | ・雑踏警備の経験が豊富で、信頼できる警備会社を選ぶ ・警備会社のWebサイトや資料などで、実績や資格、サービス内容などを確認する ・複数の警備会社に見積もりを依頼し、比較検討する |
| 警備会社へ相談・見積依頼 | ・イベント概要を伝えて相談 ・必要な警備体制や人数、費用の見積もりを依頼 |
| 警備計画の作成 | ・警備会社が動線や混雑予想をもとに、警備配置や対応策を計画。必要に応じて主催者と打ち合わせを行う |
| 契約締結 | ・警備内容や費用に合意後、正式に契約を結ぶ |
| 関係機関への届出(必要な場合) | ・大規模イベントの場合は、警察や消防などへの事前届出や協議が求められる場合がある |
| 当日警備の実施 | ・検定合格警備員を含むスタッフが、計画に基づいて現場で警備業務を行う |
イベントの規模や内容に応じて、流れや必要な手続きが変わることがあります。
雑踏警備の強化・効率化に監視カメラを検討しよう

雑踏警備は、多くの人が集まるイベントや行事で事故や混乱を防ぎ、安全を確保するための業務です。雑踏警備には人手不足やコスト増加などの課題もありますが、監視カメラの活用による効率化が注目されています。
なお、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施している小型ボディカメラ「G-POKE」は、初期費用・往復送料0円で、1ヵ月からレンタルできるため、短期のイベント警備や一時的に警備が必要なシーンにも適しています。MIYOSHIの「G-POKE」を使って警備業務を効率化した警備会社の取り組みを下記にまとめていますので、ぜひご覧ください。