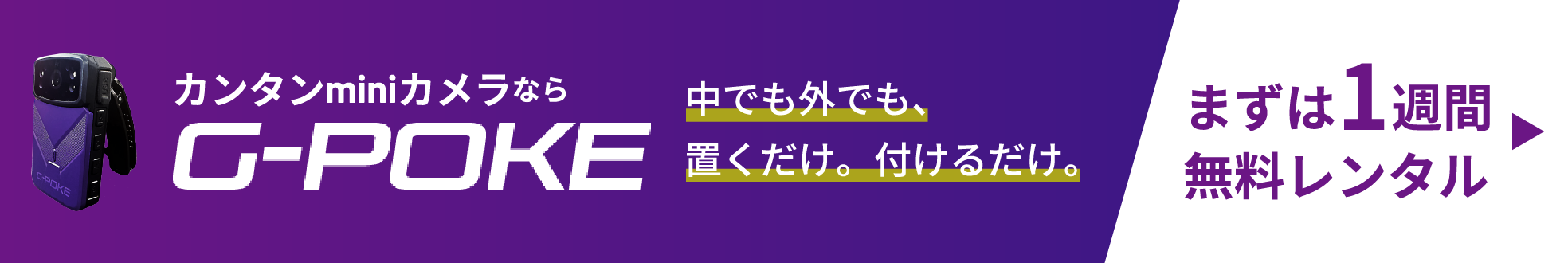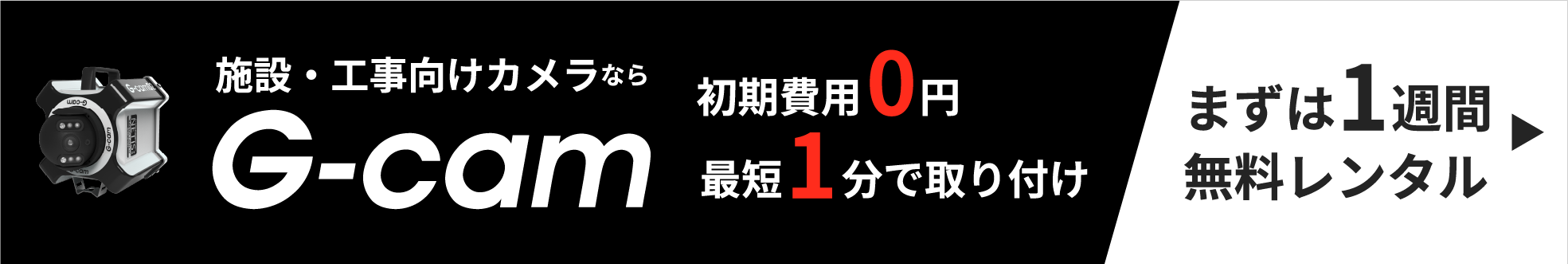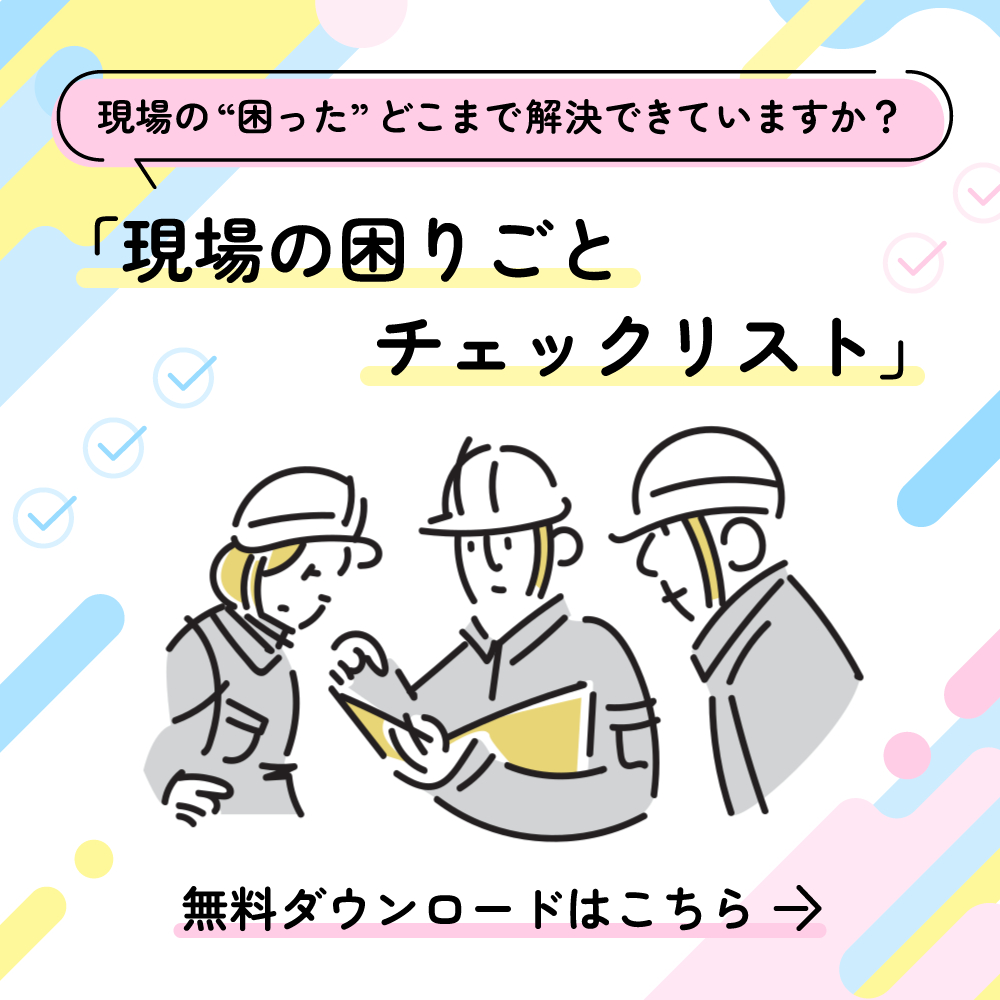不安全行動とは、安全ルールを守らない、あるいは危険を理解しながらもリスクのある行動をとる行為です。労働災害の約96%が「不安全行動」を含む原因で発生しており、現場で「つい」やってしまう不安全な行動は、重大な事故へとつながりかねません。
本記事では、不安全行動の定義や労働災害の事例、なぜ人は危険性を理解しながらも行動してしまうのかという背景を解説します。
なお、現場での不安全行動を「見える化」する手段の一つとして、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam(ジーカム)」やハンズフリーで利用できる小型カメラ「G-POKE(ジーポケ)」の活用がおすすめです。
初期費用0円、月額9,800円〜レンタル可能で、初期費用を抑えて導入できます。
実際に起きた行動を記録しておくことで、「なぜその行動が発生したのか」を客観的に分析でき、再発防止につながる具体的な対策を立てやすくなる「G-cam」「G-POKE」についての詳細は、下記から資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
不安全行動とは?不安全状態との違い・労災との関係も解説

厚生労働省では、不安全行動を下記のように定義しています。
不安全行動とは、労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為をいいます。
また、厚生労働省が「不安全行動の類型」として挙げている項目は次の12項目です。
【労働者の不安全行動】
1.防護・安全装置を無効にする
2.安全措置の不履行
3.不安全な状態を放置
4.危険な状態を作る
5.機械・装置等の指定外の使用
6.運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等
7.保護具、服装の欠陥
8.危険場所への接近
9.その他の不安全な行為
10.運転の失敗(乗物)
11.誤った動作
12.その他
つまり不安全行動とは、「危険だと認識していながらも、意図的にルールを破ったり、安全措置を怠ったりする行為」や、「慣れや油断から生じる、うっかりミス」などを指します。
不安全行動と不安全状態の違いとは?
不安全行動と不安全状態の違いは、「人が原因」か「環境が原因」かにあります。不安全行動が「作業者の行動」に起因するものに対し、不安全状態とは「環境側の問題」をさします。
例えば、ヘルメットをかぶらない、安全手順を守らないなどは「不安全行動」、床が濡れていて滑りやすい、作業通路に障害物がある、などは「不安全状態」です。2つの違いを一覧にしてみました。
| 分類 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 不安全行動 | 「人」が原因となる危険な行動 | ・保護具の未着用 ・確認不足による誤操作 |
| 不安全状態 | 「環境や設備」が原因の危険な状態 | ・照明不良で暗い ・足場がぐらついている |
多くの労働災害は、足場が不安定(状態)な場所で安全帯を使わない(行動)」のように「不安全行動」と「不安全状態」が重なったときに発生すると考えられています。
労働災害の約96%が「不安全行動」を含む原因で発生
厚生労働省の「労働災害原因要素の分析(平成22年)」によると、労働災害の発生原因の分類は、下記のとおりです。
| 分類 | 割合 |
|---|---|
| 不安全行動+不安全状態 | 94.7% |
| 不安全行動のみ | 1.7% |
| 不安全状態のみ | 2.9% |
| その他 | 0.6% |
96.4%の労働災害が「不安全行動」を含む原因で発生しています。職場の安全性を高めるためには、不安全行動をいかに減らすかがポイントです。
なお、不安全行動を減らす方法の一つとして監視カメラの設置も効果的です。例えば、株式会社MIYOSHIのカンタン監視カメラ「G-cam」を導入した清水建設株式会社様の事例では、現場の効率化と安全管理の両立を目的に、タワークレーンに「G-cam」を設置しました。
カメラを通じて事務所にいながら不安全行動の有無を確認できる体制を整え、現場管理の質とスピードを向上させています。
「G-cam」は、初期費用・往復送料0円で1ヵ月からレンタルできるため、短期工事や一時的な監視が必要な現場にも適しています。
本部や安全管理担当者が、遠隔から複数現場を同時にチェックすることもでき、現場に常駐せずとも「見て、伝えて、改善する」体制を構築できます。「G-cam」についての詳細は、下記から資料をダウンロードしてご覧ください。
\ 1週間の無料お試しもできる! /
不安全行動の事例|よくある労働災害の原因と対策

過去に発生した不安全行動による労働災害の事例をもとに、どのような行動が事故につながったのか、原因と再発防止のための対策を紹介します。
- 【安全帯不使用】ダクトの補強工事中に天井板が抜けて墜落
- 【手順書無視・保護具未着用】路上設置型変圧器の取替え工事中に感電
- 【保護具性能不足・教育未実施】橋梁塗装の剥離作業中に有機溶剤中毒および化学熱傷
事例1.【安全帯不使用】ダクトの補強工事中に天井板が抜けて墜落

【概要】
空調ダクトの補強作業中、作業員が天井裏に入り、天井板の上に乗って移動していたところ、板が抜けて約3m下に墜落。胸部や肩などを強く打ち、重傷を負った。
【原因】
- 安全帯を使用していなかった
- 現場監督者による指導・確認が不十分だった
- 作業者本人が、安全帯の必要性を軽視していた
- 天井板に人の体重を支える十分な強度がなかった
【対策】
- 作業前に天井材の強度確認を行う
- 強度が不十分な箇所では、必ず仮設足場を設置する
- 安全帯の使用を徹底させ、監督者が装着状況を確認する
- 高所作業に関する安全教育を繰り返し実施する
事例2.【手順書無視・保護具未着用】路上設置型変圧器の取替え工事中に感電
【概要】
作業者Aは、班長Bおよび警備員と3名で路上設置型変圧器の取替え工事を実施。
前日までに損壊した変圧器本体の交換および変圧器の1次側コネクタと電力供給ケーブルの接続は終了していたが、当日、作業者Aが変圧器の2次側コネクタと電力供給ケーブルの接続作業を実施していた際、感電した。
【原因】
- 作業手順書に基づく作業が行われていなかった
- 作業者Aが感電防止のための絶縁用保護具を着用していなかった
- 班長Bが作業の監督を十分に実施していなかった
- 作業者Aが電源が遮断されていないことを確認せずに作業を開始した
【対策】
- 作業手順書を作成し、全作業者に周知徹底する
- 感電防止のための絶縁用保護具の着用を義務付け、着用状況を確認する
- 作業中は班長が作業の監督を行い、安全確認を徹底する
- 作業開始前に電源が遮断されていることを確認し、必要に応じて通電遮断の措置を講じる
事例3.【保護具性能不足・教育未実施】橋梁塗装の剥離作業中に有機溶剤中毒および化学熱傷
【概要】
橋梁の旧塗膜を剥がす作業中、つり足場内で作業していた2名の作業者が有機溶剤中毒および化学熱傷を負った。2人は途中から作業に加わり、床に背中や腕をつける姿勢で作業していたが、剥離剤が作業着に浸透し皮膚に付着。意識混濁を起こすとともに、化学熱傷が発生した。
【原因】
- 被災者が床に接触する姿勢で作業を実施していた
- 作業着が液体剥離剤に対する耐性を備えていなかった
- 化学防護服(不浸透性の衣類など)を着用させていなかった
- 途中入場の作業者に対し、剥離剤の危険性に関する教育が実施されていなかった
【対策】
- 安全な作業姿勢と手順を踏まえた作業標準を作成し、教育・徹底を図る
- 不浸透性の保護衣、手袋、長靴など適切な保護具を着用させる
- すべての作業者に対し、使用する化学物質の危険性や取り扱い方法について事前教育を実施する
- 剥離作業時には皮膚接触を最小限に抑える工夫(姿勢・マットの敷設など)を行う
なぜ不安全行動をしてしまうのか?2つの要因

ここでは、厚生労働省の「安全行動を確保するマネジメントのために」を参考に不安全行動の理由を2つ紹介します。
不安全行動は、大きく「意図的な行動」と「非意図的な行動」に分類されます。
要因1.意図的な不安全行動(危険敢行行動)
危険敢行(かんこう)行動とは、作業者が安全ルールや手順を知っていながら、効率や慣れなどを理由に意図的に逸脱する行動のことです。
背景にある要因は大きく次のとおりです。
|
例えば、「高所作業時に安全帯を着用しない」「機械の停止を待たずに清掃作業を行う」などが該当します。
要因2.非意図的な不安全行動(ヒューマンエラー)
ヒューマンエラーは、作業者が意図せずにおこなってしまうミスや判断の誤りのことです。
下記のようなケースが考えられます。
|
「操作手順を誤って機械を誤作動させる」「保護具の着用方法を誤る」などが「非意図的な不安全行動」の一例です。不安全行動が起きた要因を理解することで、再発を防ぐために必要な教育や環境改善など、より効果的で的を絞ったアプローチを検討しやすくなります。
従業員の安全意識向上につながる取り組みとして、「安全大会」があります。下記の記事で目的や内容、大会成功へのヒントなどを紹介していますので、ご覧ください。
不安全行動を防ぐ4つのポイント

厚生労働省が推奨する方法をベースに、不安全行動を防ぐためのポイントを4つ紹介します。
| 1.人間を対象とした対策(安全教育・意識啓発) 2.管理を対象とした対策(安全管理体制の整備) 3.作業方法を対象とした対策(安全な作業方法の確立) 4.作業環境・設備を対象とした対策(物理的対策) |
不安全行動を防ぐためには、現場の個人・仕組み・作業・環境という4つの視点からバランスよく対策しましょう。それぞれの対策視点ごとに具体的な取り組み例を整理し、表にまとめました。
| 対策カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 安全教育・意識啓発 | KYT(危険予知訓練)、OJT、ヒヤリハット事例の共有、安全ポスターの掲示 など |
| 安全管理体制の整備 | リスクアセスメントの実施、作業手順書の整備、安全衛生委員会の運営 など |
| 安全な作業方法の確立 | 作業手順の標準化、カメラによる作業映像の活用 など |
| 物理的対策 | 保護具の配置、動線の確保、照明の最適化、安全装置の点検 など |
なお、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施する「G-POKE」は、胸やヘルメットに装着しハンズフリーで現場の様子を映せる小型カメラです。
現場で撮影したライブ映像を、本社などの離れた場所から遠隔で確認できるため、リアルタイムで遠隔からの作業指導や不安全行動の早期発見が可能です。
安全な手順への見直しや不安全行動の早期是正を図る手段として、「G-POKE」の下記のような機能が役立ちます。
(※)録画ボタンを押す数秒前の映像を自動保存する機能 |
初期費用0円、月額9,800円からレンタル可能で、短期工事やスポット利用にも初期費用を抑えて導入しやすい「G-POKE」については、下記から資料をダウンロードしてご覧ください。
\ オンライン・オフラインどちらでも使用可! /
事業者に義務付けられている「労働安全衛生法」とは

労働安全衛生法は、事業者(企業や事業主)に対して、労働者を守るための具体的な措置や体制づくりを義務付けている法律です。
目的は、下記のように法律で定められています。
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
なお労働安全衛生法では、労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更したときに下記の項目について安全衛生教育の実施を義務付けています。(必要に応じ1~4の項目は省略可能)
| 1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること 2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること 3.作業手順に関すること 4.作業開始時の点検に関すること 5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 6.整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること 7.事故時等における応急措置及び退避に関すること 8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 |
参考:1 労働災害はなぜ発生するのか
まとめると、事業者には労働者の安全と健康を守る責任があり、それを果たすために労働安全衛生法に基づいた教育や環境づくりが欠かせないということです。
現場で使える!不安全行動チェックリスト

最後に、岡山労働局が提供する資料「行動災害防止チェックリスト」 をもとに、現場で即活用できるチェックリストを作成しました。
日々の作業前点検や安全パトロール時に活用し、労働災害の防止にお役立てください。
| 【作業環境・整理整頓】 ⬜︎ 通路や階段、出口に物が放置されていないか ⬜︎ 床の水たまり、油、粉類などが放置されていないか ⬜︎ 滑りやすい場所に注意喚起の標識が設置されているか ⬜︎ 作業場の4S(整理・整頓・清掃・清潔)が実施されているか 【転倒・腰痛予防対策】 ⬜︎ 作業に適した滑りにくい安全靴を着用しているか ⬜︎ 作業前にストレッチや体操を実施しているか ⬜︎ 重量物の取り扱い時に適切な姿勢を保っているか ⬜︎ 作業姿勢や動作手順が無理のないように計画されているか 【作業管理・教育】 ⬜︎ 作業手順書が整備され、作業者に周知されているか ⬜︎ 作業開始前に危険予知活動(KYT)を実施しているか ⬜︎ 作業者に対して定期的な安全衛生教育が行われているか ⬜︎ 作業計画が書面で作成され、関係者に周知されているか 【機械設備・フォークリフトの安全管理】 ⬜︎ フォークリフトの爪を昇降ステップとして使用していないか ⬜︎ フォークリフトから離れる際に爪を最下部まで下げているか ⬜︎ カゴ車の車輪ストッパーが使用されているか ⬜︎ 機械設備の作業開始前点検が実施されているか |
なお、完全版は下記からご覧ください。
不安全行動ゼロへ!「G-cam」で現場の見える化を始めよう

不安全行動は、作業者の「慣れ」や「思い込み」が招くものも多く、ルールだけでは防ぎきれません。
本記事で紹介した対策やチェックリストと併用して、安全文化の定着に向けた仕組みづくりを進めましょう。
なお、株式会社MIYOSHIが提供する「G-cam」「G-POKE」は、不安全行動の振り返りや安全教育の教材としての活用にもおすすめです。
営業日15時までのご注文ですぐに全国どこでも無料でお届け、返却も無料なので現場の負担が少なく、すぐに監視をスタートできます。加えて1週間の無料お試しも実施中で、現場での使用感を導入前にお試しいただけます。
SIM内蔵でWi-Fiがない環境でもご利用いただける「G-cam」「G-POKE」については、下記からお気軽に資料をダウンロードしてご覧ください。