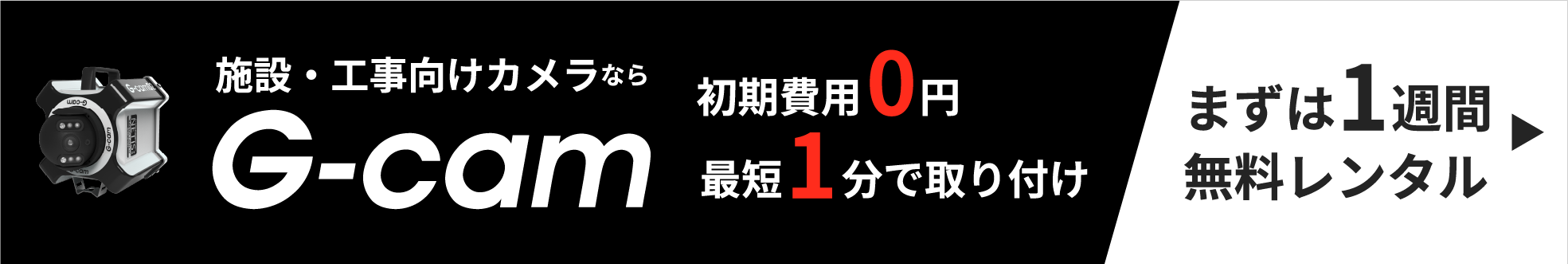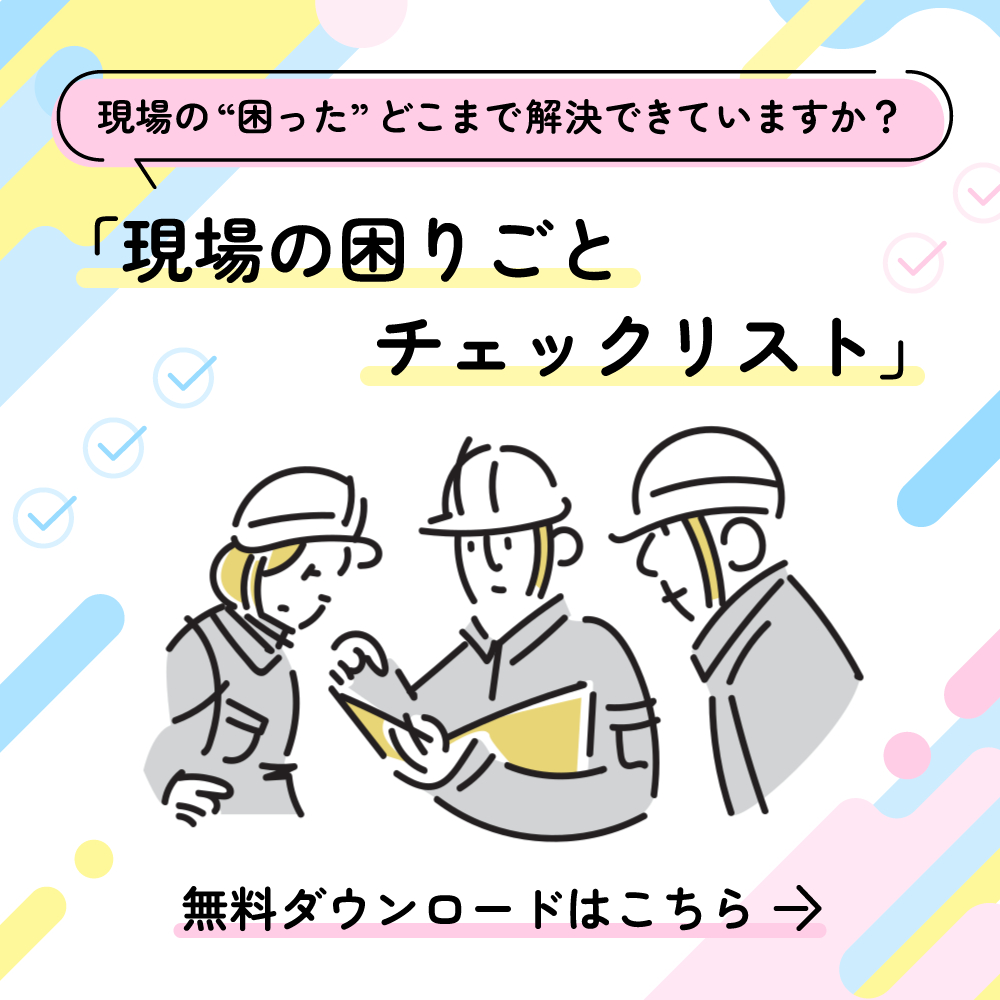安全配慮義務とは、労働契約法第5条に基づく「使用者が労働者の生命や健康を守る責任のこと」をさします。違反すると多額の賠償責任や企業の信用失墜のリスクにつながりかねません。
本記事では、安全配慮義務違反が認定された代表的な事例と裁判所の判断基準を詳しく解説し、今すぐ実践できる具体的な対策を紹介します。記事を読むことで、安全配慮義務違反のリスクを軽減し、従業員と企業を守る方法の理解につながります。
なお、下記の記事では安全配慮義務について網羅的に解説していますので、併せてご覧ください。
目次
安全配慮義務違反で企業責任が問われた事例7選

ここでは、最高裁判決を含む「安全配慮義務違反で企業責任が問われた」7つの事例を紹介します。
職場の安全対策や労働環境の改善を検討する際に、ぜひこれらの事例を参考にしてください。
事例1.陸上自衛隊事件
- 【概要】
- ・昭和40年7月13日、陸上自衛隊員Aが自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックにひかれて死亡した
- ・遺族は、「隊員が安全に作業できるよう安全確保の配慮を怠った」として国に損害賠償を求めて訴えを起こした
- 【判決内容】
- ・国は給与支払い義務だけでなく、公務員が働く場所や施設の安全を確保する義務(安全配慮義務)を負うと判断(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決)
これにより、公務員に対しても安全配慮義務が及ぶことが初めて明確に認められました。
- 【どこが問題だったのか?】
- ・危険な作業環境での事故リスクを想定していながら、十分な安全対策を取っていなかった
- ・車両整備の現場における動線管理や安全確認体制が不十分だった
- ・「事故を防ぐ手立てを講じられたのに怠った」と裁判所に認定された
この判例は「従業員の安全を守るのは給料を払う以上に重い義務」という考え方を確立しました。つまり、設備投資や安全マニュアル整備を怠ることは、企業にとって高額な損害賠償リスクにつながるという事例です。
事例2.川義事件
- 【概要】
- ・会社の宿直勤務を命じられた従業員Aが、1978年8月13日午前9時から24時間の宿直勤務中、社屋内で盗賊に侵入され殺害された
- ・遺族は会社に対し、宿直勤務を命じた使用者として従業員の生命・身体を危険から保護すべき義務を怠ったとして、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を求めて訴えを起こした
- 【判決内容】
- ・使用者には報酬支払義務だけでなく、労働者の生命・身体を危険から守る安全配慮義務があると判示
- ・宿直勤務を命じる以上、侵入防止設備の設置や複数人配置、安全教育などを行うべきであったとし、企業の義務違反を認定(1984年4月10日:最高裁第三小法廷判決)
- 【どこが問題だったのか?】
- ・危険が予見できる宿直勤務に対し、侵入防止や緊急時の避難策を用意しなかった
- ・宿直員を1人に任せるなど、安全体制が脆弱だった
リスクが予見できる業務に従業員を配置する場合、設備や人員の配置・安全マニュアル整備が不可欠という事例です。
事例3.電通事件
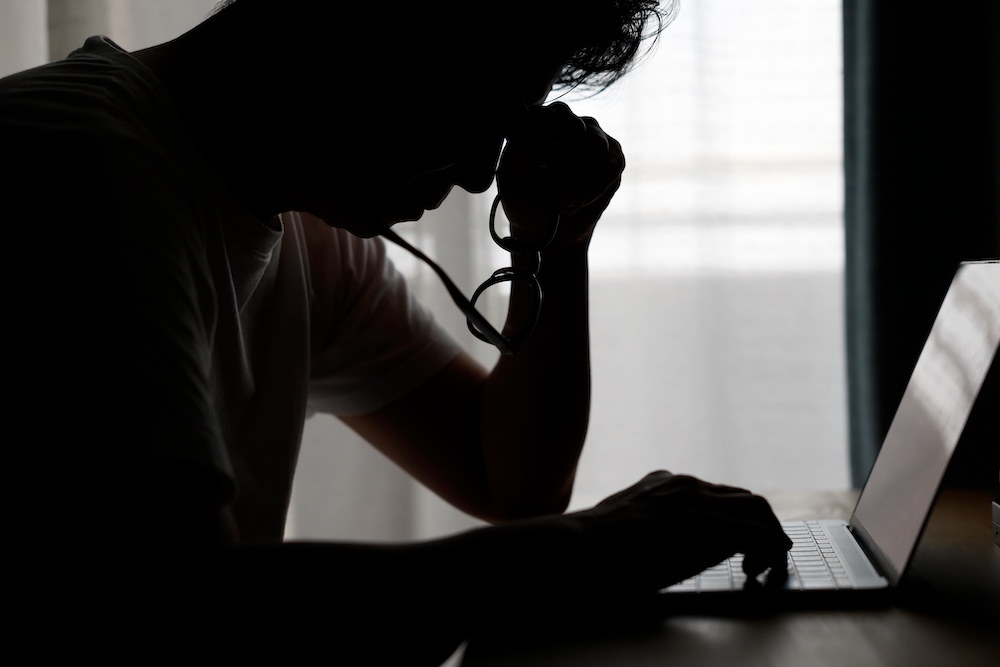
- 【概要】
- ・1990年4月に入社した新入社員A(男性・24歳)が、慢性的な長時間労働に従事する中でうつ病を発症し、入社1年5ヵ月後の1991年8月に自殺した
- ・配属後から深夜帰宅が続き、1991年1月以降は帰宅しない日も発生。同年7月には顔色が悪化し、8月には「自信がない、眠れない」と上司に訴えたほか異常行動もみられた
- ・遺族である両親が、長時間労働による心身の疲労蓄積を防止すべき安全配慮義務を怠ったとして会社に損害賠償を請求した
- 【判決内容】
- ・最高裁(2000年3月24日)は、長時間労働によるうつ病発症から自殺に至る因果関係を認めた
- ・過労自殺における民事損害賠償請求で因果関係を認めた、初の最高裁判決となった(2000年3月24日:最高裁第二小法廷判決)
- 【どこが問題だったのか?】
- ・使用者は業務管理において労働者の心身の健康を損なわないよう業務の配分・管理する義務があり、指揮監督権限を持つ上司も、この義務に沿って注意すべき立場にある
- ・それにも関わらず、上司らがAの長時間労働と健康悪化を認識しながら負担軽減措置を取らなかった
不眠や自信喪失などの兆候を見ていた上司や会社がどれだけ手を打てたかが、この判例の重要なポイントです。
- 負荷の見える化
- 早期の業務調整
- 医療・産業医の連携
これらを「当然の義務」ととらえておくことが、安全配慮義務への対策の第一歩ともいえます。
「業務の現状把握と早期の改善」は、安全配慮義務において大切な施策の一つです。そのためには、監視カメラによる現場の可視化が有効です。
なお、株式会社MIYOSHIが提供するカンタン監視カメラ「G-cam」は初期費用・送料無料、月額9,800円(税別)から使用できるレンタルカメラです。モバイルSIMを内蔵しているため、遠隔から職場や現場の様子を確認でき、長時間労働や夜間作業の実態を可視化できます。早期に業務負荷を把握・調整できることで、従業員の健康と企業のリスク低減の両立にも役立ちます。
1週間の無料レンタルも実施中で、使用感をお試しいただける「G-cam」の詳細は、下記から資料をダウンロードしてご確認ください。
\営業日15時までのご連絡で即日発送! /

事例4.B事件
- 【概要】
- ・市水道局の職員(29歳、男性)が、配属先の課長、係長、主査から継続的に侮蔑的な言動を受け、それを苦にして自殺した
- ・職員は、異性経験や容姿に対する嘲りやからかう言動に加え、ナイフを突きつけられ「これで刺してやる」と脅されるなどの言動を受けていた
- 【判決内容】
- ・高裁は、市の安全配慮義務違反による損害賠償を認定した
- ・行為者である上司個人に対する責任については、「公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国または地方公共団体がその被害者に対して賠償の責任を負うべき」として、賠償責任を専ら市のみに認めた
- ・上司には個人としての賠償責任を負わせなかった(2003年:高裁判決)
参考:職場のいじめ・嫌がらせ問題について|厚生労働省労働基準局
- 【どこが問題だったのか?】
- ・課長・係長らは、主査を中心としたからかい・脅しなどのいじめを認識していたのに、制止・謝罪・配置転換などの適切な措置をとらず、むしろ同調したり些細な問題だととらえたりしていた
- ・心因反応などの精神疾患では自殺リスクが高いことは一般的に知られており、いじめを認識していた管理者には「重大結果の予見可能性」があった
- ・それにも関わらず、適切な措置を怠った
いじめは「見ていた・知っていた」時点で無関係とはいえません。気付いた時点でいじめを止める対策をすることが、何よりも重要です。
事例5.A事件

- 【概要】
- ・病院に勤務する看護師(21歳、男性)が、男性看護師の間では先輩の言動が絶対という環境の下で、先輩から約3年間にわたり継続的に私用の買い物や家の掃除、風俗店への送迎、勤務時間中のパチンコ屋での順番待ち、ウーロン茶を3千円で買わせるなどの使い走りをさせられた
- ・さらに彼女とのデート中に呼び出されたり、仕事でミスした際に手を出される、勤務中に「死ねよ。」などの暴言を受けたりするなどの嫌がらせやいじめを受け、それを苦にして自殺した
- 【判決内容】
- ・地裁は、先輩看護師の行為について「悪ふざけや職場の先輩のちょっと度を超した言動であると認めることは到底できない」と判示し、行為者の不法行為による損害賠償を認定した
- ・さらに病院に対しては、いじめが3年近くに及んでいたことなどから、病院はいじめを認識することが可能であったにもかかわらず、認識した上で防止する措置を採らなかったとして、安全配慮義務違反による損害賠償を認定した(2004年:地裁判決)
参考:職場のいじめ・嫌がらせ問題について|厚生労働省労働基準局
- 【どこが問題だったのか?】
- ・先輩による私的雑用の強要・暴言・脅し・飲酒強要などは「悪ふざけ」の域を超えた違法行為である
- ・また、それによる自殺リスクの予見可能性があったにもかかわらず対処しなかった
- ・病院は、長期・反復・公然化(旅行・会議での露見)という客観状況からいじめの認識可能性があったのに、制止・調査・配置転換などの防止措置を怠った
この判例が示すのは、「知らなかった」では済まされないという厳しい現実です。企業は職場の異変に気付く仕組みを整え、問題を放置しない体制を構築する必要があります。
事例6.富士通四国システムズ事件
- 【概要】
- ・入社2年目のシステムエンジニアX(研修中)が、恒常的な長時間労働・不規則勤務を続けた結果、うつ病などを発症。退職後、企業Yに対し安全配慮義務違反を理由に損害賠償を提起した
- ・Xは月に5回程度遅刻し、昼過ぎに出社して社内の恋人と会ってから仕事を始め、夜中や早朝まで残って作業に従事
- ・発症直前6ヵ月の平均月間残業時間数は105時間超、産業医面談の対象は14回とされる
- ・会社側は「早く帰るよう」などの助言・指導を実施していたが、Xは従わなかった
- 【判決内容】
- ・Xの言動は「社会的未成熟」による側面があっても、入社後間もない不適応を過大評価すべきではないとし、個人的要因の強調は相当でないと判示した
- ・使用者側は助言のみでは不十分。状況是正の見込みが乏しい段階では、「これ以上の残業を禁止する」旨の強い指導、それでも従わなければ入館禁止や帰宅命令といった業務命令まで含め、長時間労働を物理的に止める措置をとるべき注意義務があったと認定した
- ・会社の安全配慮義務違反を認め損害の一部を認容したが、Xの勤務態様の問題性にも触れ、過失相殺(※)の類推適用による減額が示された(2008年5月26日:大阪地判)
(※)過失相殺とは、加害者側に全面的に賠償責任を負わせることが公平でない場合、損害賠償額を減額する制度のこと
- 【どこが問題だったのか】
- ・6ヵ月の平均月間残業時間数は105時間超、産業医面談の対象は14回という明確な兆候があったにもかかわらず、助言止まりで就業命令などの実効策に踏み込まなかった
- ・遅刻と深夜長時間の組み合わせが生活リズムを崩し疲労を増幅させる点を裁判所は重視。労働時間の「量」だけでなく「質(時間帯・回復機会)」を管理できていなかった
- ・従業員の未成熟や身勝手さが見られても、業務起因の強度の心理的負荷が恒常化していた以上、使用者の軽減義務は免れない
長時間労働の兆候が明確であれば、企業は「本人の意思」に委ねるのではなく、強制的に労働を止める責任があります。助言では改善しない状況こそ、より踏み込んだ管理が求められます。
事例7.東芝事件
- 【概要】
- ・大手電機メーカーに入社10年目のXが、プロジェクトリーダー就任後に過重な業務負担の中でうつ病を発症し、休職期間満了により2004年9月に解雇された
- ・Xは2000年11月にプロジェクトリーダーとなったが、不眠症などの不調を訴えるようになった
- ・業務の軽減を申し入れたが認められず、さらに業務を追加された結果、体調が悪化し「うつ病」を発症
- ・Xは、うつ病の発症は過重な業務が原因であるとして、解雇無効による地位確認と賃金、慰謝料などを求めて提訴した
- 【判決内容】
- ・一審の東京地裁は、大手電機メーカーがXの業務を軽減しなかったことは安全配慮義務違反にあたるとした
- ・東京高裁は、Xが通院や病名をメーカーに報告しなかったことを理由に過失相殺を認め、損害賠償額を減額した
- ・最高裁は、労働者の精神的健康に関する情報はプライバシーに属し、過重な業務が続く中では本人からの積極的な申告は期待し難いと指摘
- ・従業員が通院や病名を申告しなかったことを理由とする過失相殺はできないと判断し、東京高裁の判決を一部破棄し差し戻した(2014年3月24日:最高裁第二小法廷判決)
- 【どこが問題だったのか】
- ・従業員が業務軽減を申し入れたにもかかわらず、それを認めずさらに業務を追加し体調悪化を招いた
- ・体調不良の兆候が客観的に看取される状況であったにもかかわらず、従業員からの病名申告がないことを理由に対応を怠った
- ・精神的健康情報はプライバシーに属するため、過重労働下では従業員から積極的な申告を期待できないという前提を欠いていた
企業は、従業員が病名や通院の事実を申告しなくても、体調不良の兆候が見られれば対応する義務があります。
「本人が言わなかった」は免責の理由にはならず、過重労働が続く状況では企業側からの積極的な配慮が必要です。
安全配慮義務違反のリスクを軽減する3つのポイント

安全配慮義務違反を防ぐためには、裁判所が重視する判断要素に対して確実に対応できる体制を整えることが欠かせません。本章では、次の3つのポイントで企業が取るべき具体的な対策を解説します。
これらの対策を実践することで企業の落ち度を防ぎ、安全配慮義務違反のリスクを大幅に軽減できます。それぞれの詳細を確認し、自社の安全管理体制の強化に役立ててみてください。
ポイント1.予見可能性|リスクの早期発見
- 【予見可能性とは?】
- 企業が事故や健康被害の危険性を事前に察知し、適切に対応できる体制を整えること
- 実務上の対策例
・長時間労働(月80時間超の蓄積)の自動検知システム導入
・従業員からの体調不良申告を受け付ける窓口設置
・産業医・上司による定期的な健康観察とレポート体制の構築
・ハラスメント相談窓口の設置
これらの「予兆」を見逃さない仕組みを整備することが重要です。
- リスク低減のポイント
多くの労災・健康被害には何らかの予兆が見られます。長時間労働の蓄積、体調不良の申告、ハラスメントの訴え(予兆)などを記録・対応することが、結果として安全配慮義務違反のリスク軽減につながります。
ポイント2.結果回避措置|予見される危険への確実な対応
- 【結果回避措置とは?】
- 発見したリスクに対し、企業が迅速かつ適切な防止措置を実行し、事故や疾病の発生を未然に防ぐこと
- 具体的な措置の例
・長時間労働が続く場合は、医師による面接指導の速やかな実施
・業務量の見直しと人員配置の調整
・ハラスメント発生時の迅速な調査と適切な懲戒処分
・危険な設備への安全装置の設置と定期点検
- リスク低減のポイント
「リスクを認識していたのに対策を怠った」という状況を作らないことが重要です。記録に残る形で対策を実行し、その効果を検証しましょう。
ポイント3.因果関係|適切な対応の記録
- ・因果関係の立証とは?
- 企業が講じた安全配慮措置を適切に記録・保管し、万が一の際に「義務違反と損害との因果関係」を否定できる証拠を残すこと
- 記録すべき項目の例
・実施した面接指導の記録(いつ・誰が・どのような内容で面談を行ったのか)
・業務軽減措置の決定文書(誰の業務量を・どのような内容で・どれくらいの期間・正式に軽減したのか)
・ハラスメント調査報告書(相談の経緯・調査方法・結果・再発防止策を含む)
・安全装置の点検記録(点検日時・実施者・指摘事項・改善対応を明確に記録)
医学的・科学的知見に基づく対応であったことを示せる記録が重要です。
- ITツールの活用
安全管理に有効なITツールを活用することで、労働時間や健康リスクの「見える化」と対応履歴の自動記録・蓄積を実現できます。人的ミスを防ぎ、客観的なエビデンスを継続的に確保すれば、立証リスクの軽減が可能です。
- リスク低減のポイント
「企業が適切な措置を講じていれば損害は防げた」という主張を防ぐため、対応の妥当性を客観的に示せる記録体制を構築しましょう。
リスクの早期発見や迅速な対応、適切な記録の蓄積により、企業は従業員の安全を守ると同時に法的リスクからも自社を守れます。
安全配慮義務への対策には監視カメラの活用も有効

監視カメラの活用により、安全配慮義務で求められる「予見」「対策」「記録」を効果的に実現できます。
安全配慮義務への対応で監視カメラの導入を検討している方には、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」がおすすめです。
| 【安全配慮義務への対応にG-camがおすすめの理由】 ・ブラウザやアプリで複数の現場を一元管理できるため、リアルタイムで危険箇所や作業状況を把握できる ・IR夜間監視機能で暗闇でも鮮明に撮影できる ・IP66※防塵防水で荒天・夜間も継続監視が可能 ・電源確保が困難な場所でも、オプションのソーラーバッテリーで無人管理を実現 |
※IP66とは:防塵性能が6等級(粉塵が入らない)、防水性能が6等級(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)防塵防水機能を示す規格のこと
「G-cam」は、初期費用・送料無料で月額9,800円(税別)から利用できます。モバイルSIM内蔵でネットワーク設定も不要、届いたその日から設置・監視が可能です。また、レンタル形式のため1ヵ月単位で必要な期間のみ利用でき、コスト削減にも効果的です。
安全配慮義務への対応を強化したい方は、下記のボタンから資料をダウンロードしてご確認ください。1週間の無料レンタルも実施中です。
\ カメラの真下・真後ろまで広範囲の監視が可能!/

参考:高額損害賠償と減額要素の判断基準

安全配慮義務違反が認定された場合、企業が負担する損害賠償額はどの程度になり、どのような場合に減額されるのでしょうか。実際の判例をもとに賠償額の目安と減額要素について解説します。
1.賠償額の目安(認容額※)
安全配慮義務違反が認定されると、賠償額は数千万円から1億円超に及ぶことがあります。
※認容額:裁判所が請求のうち認めた金額のこと
代表的な事例として、前述した電通事件があります。電通事件では一審で約1億2,600万円、二審で減額後、最高裁破棄差戻しを経て約1億6,800万円で和解しました。事案により異なりますが、近年の傾向として判決で認められた金額(認容額)はおおむね5,000万〜8,000万円が多いとされています。なお、内訳は逸失利益+慰謝料(本人・遺族)などが中心です。
このように、安全配慮義務違反が認定されると、賠償額は企業にとって極めて大きな負担となります。
次に、賠償額の減額が認められるケースについてみていきましょう。
2.減額要素(過失相殺)の基本
企業側は、労働者にも自己管理上の落ち度があったと主張し、賠償額の減額を求める場合があります。これを「自己保健義務(自己安全配慮義務)」と呼びます。
- 自己保健義務とは?
・労働者が自分の健康・安全を守るために合理的に配慮すべき義務のこと。企業の安全配慮義務とは主体も内容も異なる - 減額が認められにくい理由
・企業の安全配慮義務のほうが重いため、自己保健義務違反を理由とする減額は限定的になりやすい
・特に過労自殺では、精神疾患の影響下での行為と評価され、過失相殺が否定される傾向がある(電通事件) - 減額が認められた例
・富士通四国システムズ事件:会社の安全配慮義務違反を認めつつ、労働者側の勤務態様も問題視され、過失相殺による一部減額が示された
安全配慮義務違反による損害賠償は高額になる傾向があり、企業経営に深刻な影響を与えます。ただし、労働者側に明らかな落ち度がある場合は減額される可能性もあるため、個別の事情を慎重に検討することが重要です。企業には日頃から適切な安全管理体制を整え、リスクを未然に防ぐ対策をすることが求められます。
安全配慮義務違反の「芽」を摘み従業員と企業を守ろう

安全配慮義務違反を防ぐためには「予兆を見逃さず」「早期に結果回避措置を講じ」「その履行を記録に残す」体制を整えることが大切です。こうした取り組みが、社員の命と健康だけでなく、自社を高額賠償リスクや信用失墜からも守ります。
重大なリスクを見落とさないためには、監視カメラのような安全管理ソリューションの活用がおすすめです。
株式会社MIYOSHIのカンタン監視カメラ「G-cam」は、初期費用・送料無料、月額9,800円(税別)からレンタルが可能です。加えて1週間の無料レンタルを実施しているため、安全配慮義務への対応強化に向けて、導入前に実際の使用感をお試しいただけます。
レンズ横回転最大350°縦回転最大90°で広範囲をカバーできるため、少ないカメラ台数で効率的な監視が実現する「G-cam」の詳細は、下記より資料をダウンロードしてご確認ください。
\ カメラの真下・真後ろまで広範囲の監視が可能!/