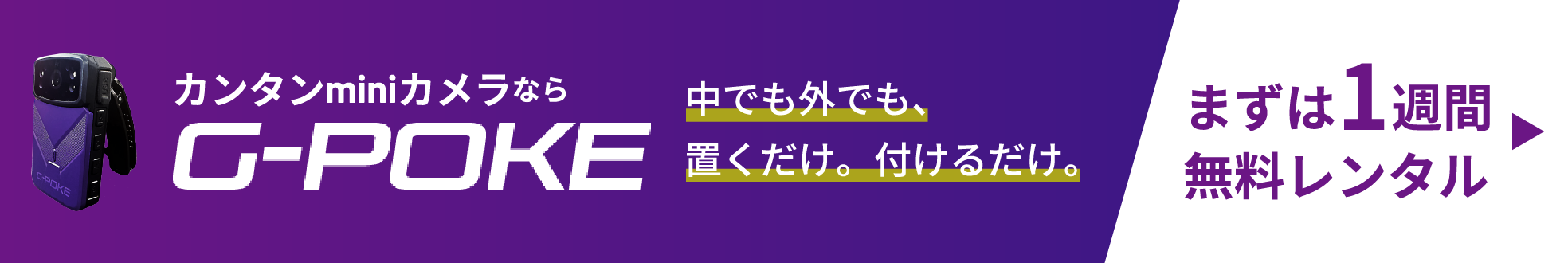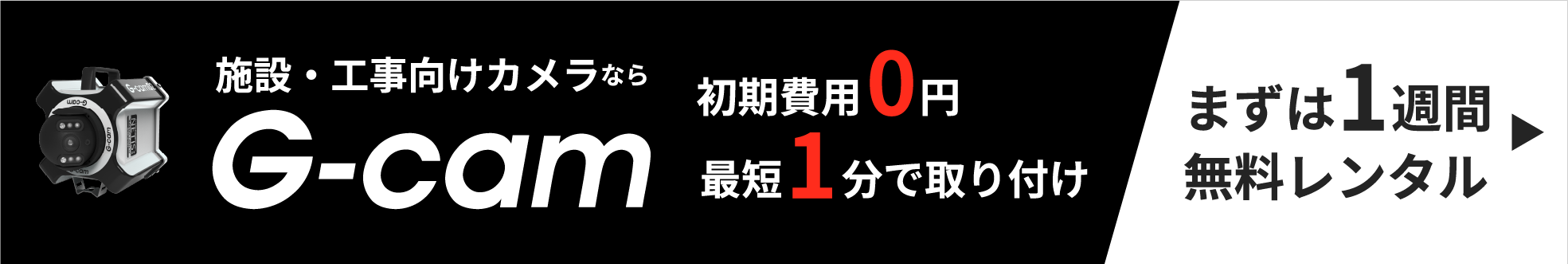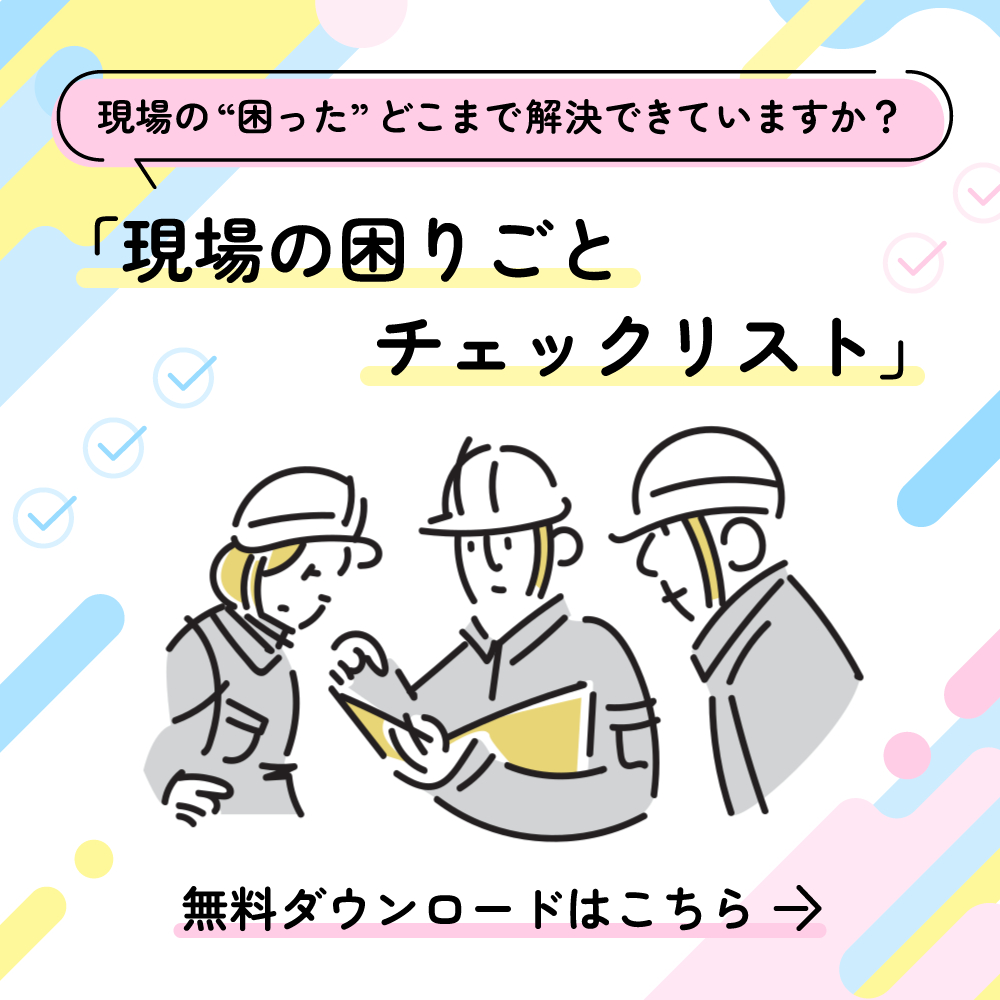近年、企業にとって深刻な課題となっているのが、顧客や取引先からのハラスメント「カスタマーハラスメント(以下カスハラ)」です。東京都で全国初のカスハラ防止条例が施行され、国レベルでも法改正の動きが進むなど、カスハラ対策は企業にとって避けて通れない課題といえるでしょう。
本記事では、最新の法規制の動向を踏まえ、企業が今すぐ取り組むべきカスハラ対策について、「準備編」と「対応編」に分けて解説します。
従業員を守り、企業価値を維持するために、今すぐできる対策として監視カメラの活用があります。
例えば、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施している小型ボディカメラ「G-POKE(ジーポケ)」は、コンセントもWi-Fiも不要で、「その場に置くだけ」胸ポケットに「つけるだけ」で撮影が可能です。
初期費用0円・月額9,800円からレンタル可能で、導入コストを抑えてカスハラ対策をスタートできる「G-POKE」の詳細は、下記からご覧ください。
\ オフライン・オンラインどちらでも使える!/
※この記事の情報は2025年4月時点の情報です
目次
カスハラ対策はいよいよ義務化へ!最新動向をチェック

結論、カスハラ対策はまだ「全国一律の法的義務」にはなっていませんが、実質的な義務化が進行中という状況です(2025年4月時点)。そして、東京都では全国初の「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が2024年10月に可決、2025年4月に施行されました。
本章では、下記の2点について紹介します。
東京都の「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」
東京都では、2025年4月1日から「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(通称:東京都カスハラ防止条例)」が施行されました。この条例は、あらゆる場において「何人もカスタマーハラスメントをおこなってはならない」と明確に定めています。
条例の主な内容は下記のとおりです。
|
東京都は条例に合わせて防止ガイドラインやマニュアルも公表しており、事業者に対し具体的な対策を促しています。
厚生労働省による「労働施策総合推進法」改正案が進行中
国レベルでは、2025年3月に厚生労働省が「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日に国会へ提出しました。この改正案には、カスタマーハラスメントへの対応強化が盛り込まれています。
法改正により、パワハラ防止措置義務が強化されるとともに、顧客等からのハラスメント(カスハラ)対策についても、事業主に努力義務として課される見込みです。
現時点(2025年4月)では、法改正はまだ施行されておらず、正式な施行日は「公布から1年6ヵ月以内」とされています。
つまり、2026年秋頃までに施行される可能性が高い状況です。
今後の法施行により、企業はカスハラへの対応を「努力義務」ではなく、実質的に避けては通れない経営課題としてとらえる必要があります。制度上の義務化は段階的に進んでいるものの、社会的にはすでに「対応していて当然」と見なされつつあるのが実情といえるでしょう。
参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び 職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省
カスハラとは?定義の確認と近年の発生状況

カスハラとは、顧客や取引先(顧客等)による過度な要求や、不当・悪質なクレーム行為のことです。
企業や業界によって基準は異なるため、法的に明確な定義はないものの、厚生労働省は次のような行為をカスハラの典型例としています。
| カスハラに該当する可能性のある言動 | ・要求内容に妥当性がない ・要求手段や態様が社会通念上不相当(怒鳴る・土下座の強要・暴言・執拗な電話など) |
|---|---|
| カスハラの被害 | ・労働者が人格や尊厳を侵害され、身体的・精神的に苦痛を受ける ・その結果、就業環境が不快になり、本来の能力が発揮できないような悪影響が出る |
| 顧客等の範囲 | ・「顧客等」には、現在の利用者だけでなく、将来的に利用する可能性のある潜在的顧客も含まれる |
厚生労働省による調査結果から、カスハラは近年、特に医療・福祉、宿泊・飲食サービス、小売業などの接客業種を中心に増加傾向にあることがわかります。
直近3年間のハラスメント相談件数について、「カスハラ(顧客等からの著しい迷惑行為)」に関する割合を業種別にみると、下記のとおりです。
|
そして、3割前後の企業がカスハラ相談の「増加」を実感しています。
ちなみに、これらの業種ではパワハラやセクハラなどの他のハラスメントも増加しており、「複数のハラスメントが同時に進行している可能性が高い」ことも指摘されています。
顧客と日常的に接する機会が多い業種ではカスハラの深刻化が顕著であり、企業としては従業員を守る仕組みや記録体制の整備が急務です。
企業がカスハラ対策をするべき3つの理由

企業がカスハラ対策をするべき主な理由を、3つ紹介します。
理由1.大切な人材を守るため
カスハラを受けた従業員は、強いストレスや精神的苦痛を抱えることになりかねません。従業員が安心して働ける環境を整える取り組みは、企業の最優先事項といえます。
下記は、不当な要求や悪質な言動に繰り返しさらされると陥りやすくなる状態です。
|
精神的なダメージが要因となって、配置転換・休職・退職に至るケースも少なくありません。接客業や医療・福祉など、対人業務が中心の現場では、人材確保が困難な状況に拍車をかける要因ともなり得ます。
人材の流出は、採用・教育コストの増加にもつながり、企業にとって大きな損失です。
理由2.企業の資源(時間・コスト・信頼)を守るため
企業がカスハラ対応に多くの時間と労力を費やすことは、「クレーム対応」の範疇を超えた経営リスクです。例えば、企業は下記のように多面的な負担を抱えるおそれがあります。
| 時間的損失 | 現場での長時間対応、謝罪訪問、社内での対策会議、弁護士相談など |
|---|---|
| 業務の停滞 | 顧客対応が優先され、他業務が遂行できない状態に |
| コスト増加 | 慰謝料や代替品の提供、新規人材の採用・教育コストなどの金銭的損失 |
| ブランド毀損(きそん) | SNSでの拡散や対応への不満により企業のイメージが悪化 |
適切な対応策を実施しない場合、企業の信頼性そのものが問われる事態に発展しかねません。
理由3.顧客満足度と売上機会を守るため
カスハラの発生は現場に居合わせた、迷惑行為を受けていない他の顧客にも下記のような悪影響を及ぼします。
|
このようにカスハラは、他の顧客の満足度の低下・売上減少・機会損失につながるおそれもあります。
次章でカスハラ対策を「準備編」と発生後の「対応編」に分けて紹介しますので、ぜひご覧ください。
【準備編】カスハラを未然に防ぐ!厚生労働省のマニュアルに基づく対策
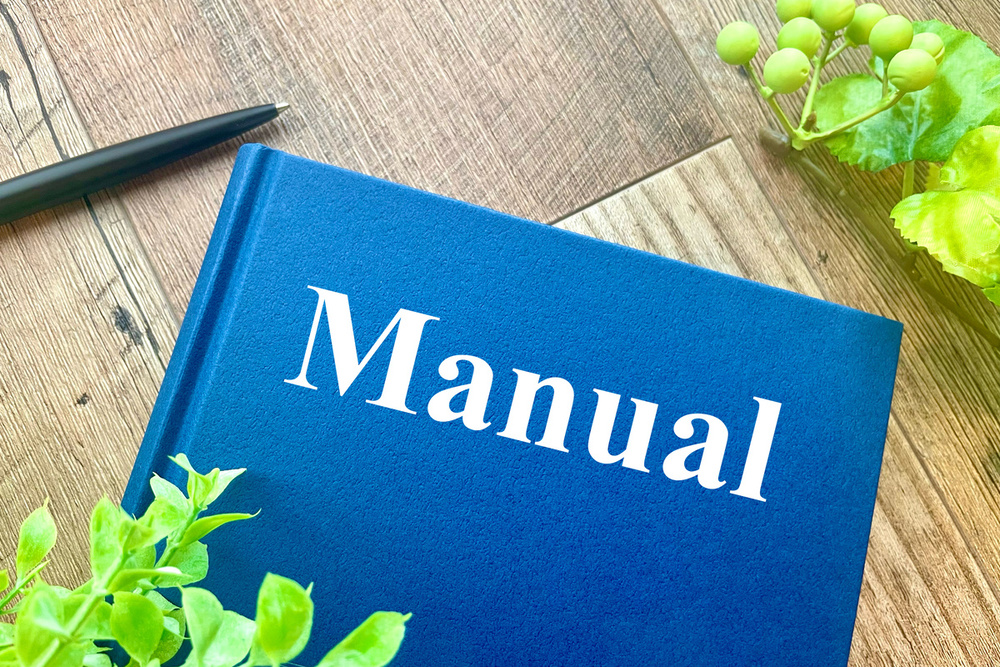
厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の中で、企業に対してカスハラを想定した「事前準備」を推奨しており、4つの基本的な取り組みを明示しています。
本章では、「準備編」として具体的な内容を解説しながら、現場ですぐに取り入れられる対策もご紹介します。
対策1.方針と基本姿勢を明確にし、従業員に周知・教育する
企業としてまず行うべきは、「カスハラに屈しない姿勢」を社内外に明確に示すことです。組織のトップが基本方針・基本姿勢を明文化し、全社員に周知しましょう。
下記の案内例のように、「不当な要求には応じない」「従業員を守るための対応を優先する」など、立場を明確にすることがポイントです。
| ▼基本方針の案内例 株式会社〇〇(または〇〇)は、お客様に最高の満足を提供することを常に目指し、誠意をもって信頼に応えるよう努めております。 しかしながら、一部のお客様からの要求や言動の中には、社会通念を逸脱し、従業員の人格を否定するような言動、暴力、セクシュアルハラスメント等、従業員の尊厳を著しく傷つける行為が見受けられます。このような行為は、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、職場環境を悪化させ、円滑な業務遂行を妨げるものであり、決して容認できるものではありません。 つきましては、当社は従業員一人ひとりの人権と尊厳を守るため、お客様からの不当な要求や迷惑行為に対し、毅然とした態度で対応し、必要に応じて組織として対応を行います。 従業員が安心して働ける環境を維持することは、お客様へのより良いサービス提供にもつながると考えています。今後も、従業員とお客様の双方にとって健全で持続可能な関係づくりを目指してまいります。 |
ポスターやWeb掲載などで社外にも周知すると、抑止効果も見込めます。
対策2.従業員が相談しやすい体制を整える
カスハラを受けた従業員が、速やかに相談・報告できる下記のような仕組みも欠かせません。
【相談できる体制づくりの例】
|
トラブル対応に慣れていない現場スタッフでも安心して声を上げられるよう、周知徹底が必要です。
対策3.対応マニュアルを整備し、判断や対応のブレを防ぐ
現場対応を属人化させず、誰でも一定水準の対応ができるようにするには、事前のルールづくりが効果的です。
【ルールづくりの例】
|
マニュアルの整備により、対応の迷いやばらつきを防ぎ、現場での対応力と安心感の向上につなげましょう。
対策4.社内研修で現場対応力を高める
顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームへの社内における対応について、従業員を教育しましょう。
【社内教育の例】
|
研修を通じて、従業員一人ひとりが自信を持って対応できる力を養うことで、組織全体の対応力が高まります。
【対応編】カスハラが発生してしまったら?厚生労働省のマニュアルに基づく対策

本章では、発生後の対応=「対応編」として、前章の「準備編」と同様に厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、企業が取るべき具体的な対処法を紹介します。
万が一、カスハラが発生してしまった場合には、従業員の安全を最優先に、適切な対応が求められます。
対策1.事実確認と対応方針の徹底
まずは、その言動がカスハラに該当するかどうか、客観的な視点での事実確認を行います。
顧客や従業員からのヒアリング、録音・録画などをもとに証拠を整理しましょう。実害や影響の有無を確認し、必要に応じて謝罪・返金・商品交換などの対応を検討します。
ルールに反した要求には毅然とした態度で対応し、妥協的な譲歩は避けるべきです。
なお、厚労省のマニュアルでも、トラブルの全体像を把握するうえで録音・録画データの活用が有効であるとされています。特に、映像や音声の保存は、後の証拠保全や社内外への説明を支える手段として有効です。
例えば、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施している小型ボディカメラ「G-POKE(ジーポケ)」は、わずか165gの軽さで身体への負担が少なく装着でき、遠隔から監視体制を整えられるほか、「置くだけ」でも撮影できるため、さまざまな場面で幅広く利用していただけます。
加えて、レジ前や受付などカスハラが起こりやすい場面で、カメラの存在による「抑止」と、通信環境に左右されずに映像を残せる「証拠保全」の両方に役立つ小型カメラです。オフライン環境でも録画が可能なため、通信状況にかかわらず確実な証拠記録を残すことができます。
初期費用0円、月額9,800円〜レンタル可能なうえ、スマートフォンで使い慣れたタッチパネル方式で導入コスト・教育コストを抑えての利用が可能な「G-POKE」の詳細は、下記をクリックのうえ資料をダウンロードしてご覧ください。
\ 「置くだけ」でもすぐに使える!/
対策2.被害を受けた従業員へのケア
カスハラ被害の後遺症は、心身の健康に深刻な影響を及ぼす場合もあります。企業は、下記のように被害者が安心して働き続けられる環境づくりが必要です。
|
被害者が孤立せずに再び自信を持って働けるよう、企業として継続的な支援を続けましょう。
対策3.再発防止に向けた取り組み
一度対応して終わりではなく、トラブルから学び、組織としての仕組みを改善することがカスハラ対策の本質です。再発防止に効果的な対策は、下記の通りです。
|
対応フローは、現場で実際に機能し、継続的に改善されていく仕組みとして運用していきましょう。
対策4.従業員全体への適切な周知と運用
最後に、対応ルールや再発防止策が「形だけでなく実際に機能」するように、次のような運用を実施しましょう。
|
このように、カスハラ対応には「事実確認」「従業員保護」「仕組み改善」「社内共有」という4つの柱が不可欠です。そして、安全を支える土台として、「正確な記録=証拠の可視化」が大きな役割を果たします。
対策の仕上げに、厚生労働省が公開している「カスタマーハラスメント対策チェックシート」で、今の職場で何ができていて、何が足りていないのかをチェックしてみましょう。
どこからがカスハラ?判断基準と代表的な行為一覧

最後に、「カスハラかどうか」を見極めるための判断基準と、代表的な事例を紹介します。カスタマーハラスメントは「クレームすべてが該当するわけではない」という点が前提です。
厚生労働省のマニュアルでは、カスハラに該当するかどうかの判断基準として、次の2点を挙げています。
【カスハラ該当の判断軸】
|
つまり、内容が合理的でも、言動が過度であればカスハラになる場合があるということです。また手段が丁寧であっても、明らかに不当な要求であればカスハラに該当します。
よくあるカスハラの例と、判断ポイントを下記にまとめました。
| 分類 | 具体例 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 威圧的な言動 | ・大声で怒鳴る ・机を叩く ・暴力的態度 | 身体的・心理的威嚇によって職場環境が脅かされる |
| 長時間拘束 | ・数時間にわたる居座り ・延々と電話をかけ続ける | 過度な対応要求で業務に支障が出る |
| 人格否定・差別 | ・容姿・学歴・性別への侮辱 ・人格攻撃 | 要求と無関係な個人攻撃による尊厳侵害 |
| 不当な要求 | ・土下座の強要・商品を無料にしろという要求 | 対価や契約範囲を超えた非合理な要求 |
| SNS等での誹謗中傷 | ・店舗名・従業員名を晒して攻撃 | 名誉毀損、営業妨害に該当する可能性もある |
| サービス外の依頼 | ・「お前がやれ」「自宅まで来い」など | 従業員の業務範囲を逸脱した要求 |
繰り返しになりますが、すべての厳しい声がハラスメントに当たるわけではありません。例えば、「商品が壊れていた」「対応が悪かった」などのサービス改善に資する意見は、正当な苦情として区別されるべきといえます。
重要なのは、要求が妥当か、伝え方が節度を保っているかどうかという観点です。
社内ルールや相談体制を整え、カスハラ対策を進めよう!

カスハラ対策の義務化が進むなかで、企業は「やらなければならない」から「やっていて当然」へと対応を進化させることが求められています。
本記事でご紹介した「準備」と「対応」の両面からの対策を実施し、カスハラから従業員を守り、健全な企業運営を実現しましょう。
なお、カスハラ対策の一つとして、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」も有用です。レンズ横回転最大350°縦回転最大90°で、真下・真後ろまで監視でき、1台のカメラでカスハラが発生しやすい受付や接客エリアの広範囲な撮影が可能です。
初期費用0円・月額9,800円〜レンタルが可能で、コストを抑えた導入ができる「G-cam」についての詳細は下記からチェックしてみてください。
\ 1週間の無料お試し後そのままレンタル可能!/