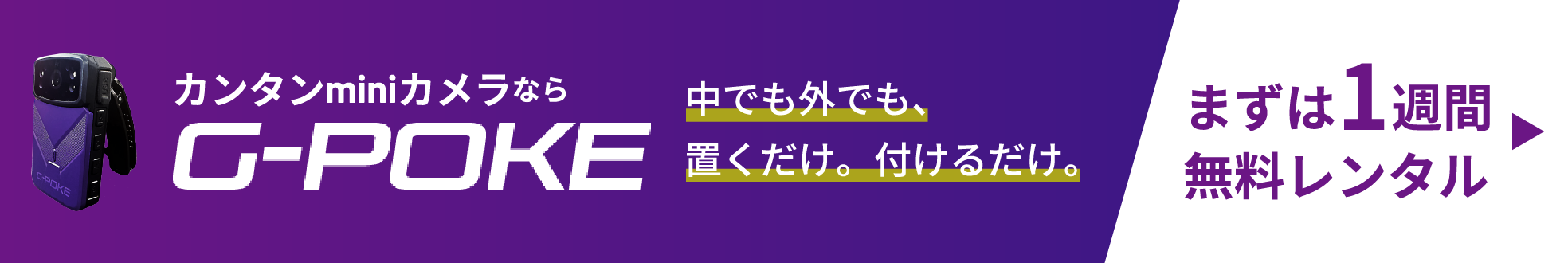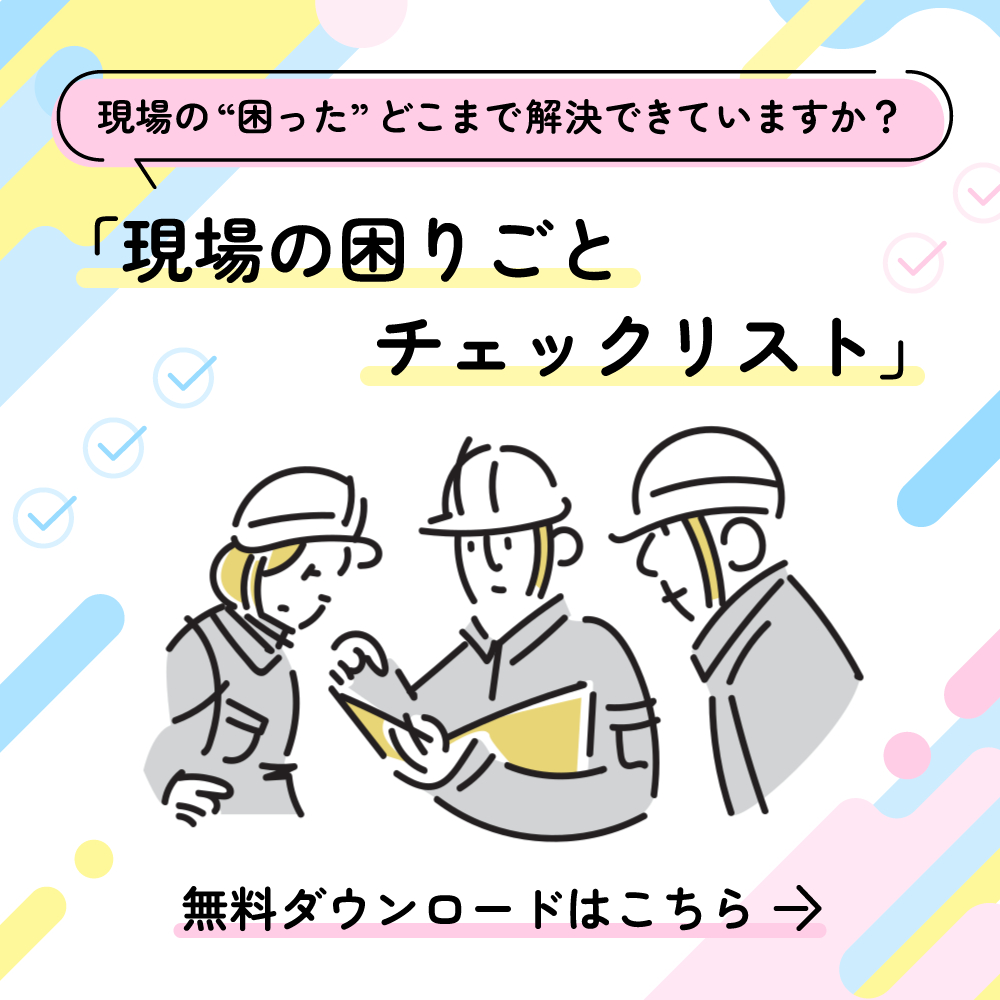危険予知活動(KY活動)は、作業前に潜む危険を予測し対策を講じることで労働災害を未然に防ぐ、極めて重要な安全管理手法です。効果的な危険予知活動を実践するためには、具体的な「危険予知活動の例文」が欠かせません。
そこで、本記事では、すぐに現場で活用できる豊富な作業シーン別の危険予知活動の例文を幅広く紹介します。
例文を参考にして危険予知活動を効率よく進め、現場の安全意識を高めたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
>>【業界別】現場ですぐに使える危険予知活動(KY活動)例文集はこちら<<
また現場のカメラ画像をもとに、危険予知活動を効率よく行うAI「tomoth」をご利用いただくことで、より効果的・効率的な運用ができます。
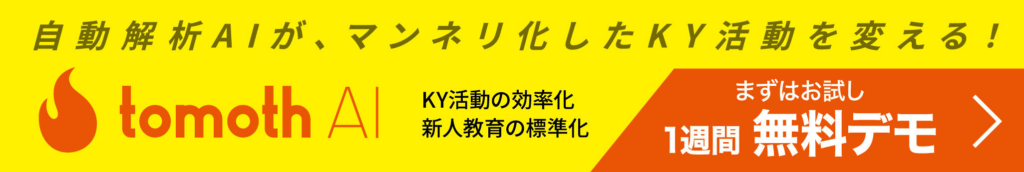
目次
危険予知活動の例文の基本!基礎4ラウンド法(4R法)

現場ですぐに使える危険予知活動(KY活動)の例文は、「基礎4ラウンド法(4R法)」にしたがって作成しましょう。
-
【基礎4ラウンド法(4R法)とは】
- 基礎4ラウンド法とは、イラストや実際の作業現場などを使って、職場に潜む危険をチームで見つけ出し、話し合い、対策を考えるという、KYT(危険予知訓練)の基本的な進め方です。
- 参考:KYT基礎4R法|厚生労働省
【危険予知活動(KY活動)の基本構成とポイント】
| ラウンド | ポイント | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1ラウンド | どんな危険が潜んでいるか (現状把握) | 現場や作業に潜む危険をできる限り多く洗い出す |
| 2ラウンド | これが危険のポイントだ (本質追求) | 洗い出した危険の中から特に重要なものを絞り込み、その本質を追求する |
| 3ラウンド | あなたならどうする (対策立案) | 重要と判断した危険ポイントに対して、具体的な対策を考える |
| 4ラウンド | 私たちはこうする (目標設定) | 実際に実施する対策を明確にし、行動目標を設定する |
【業界別】現場ですぐに使える危険予知活動(KY活動)例文集
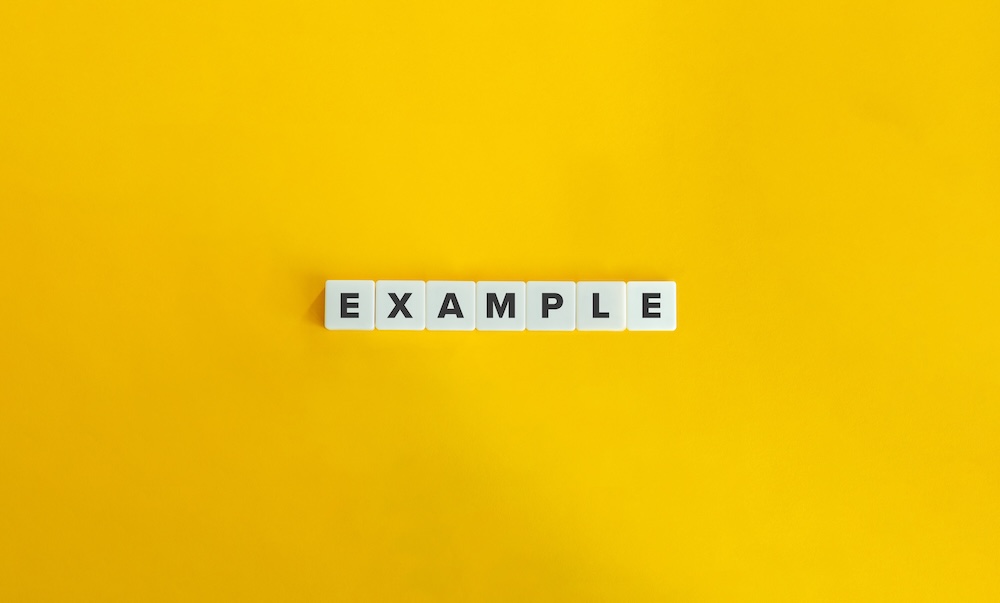
ここからは、主要な業界別に危険予知活動(KY活動)の具体的な例文を紹介します。
紹介する例文は、先ほど解説した「基礎4ラウンド法(4R法)」の構成に沿って作成しています。各ラウンドでどのような視点で危険を洗い出し、どう対策を立てていくのか、具体的な流れを掴むためのモデルケースとしてご活用ください。
※これらの例文はあくまで一例です。現場の状況や作業内容にあわせて適宜変更・追加してください。
例文1.建設業

建設業では、転倒・落下・巻き込み・感電・はさまれなどの重大災害が発生しやすく、災害の型も多岐にわたるのが特徴です。
複数業者・多人数での作業による「連携ミス」や「声かけ不足」が事故の引き金となることも多く、現場全体での危険予知と情報共有が欠かせません。
【建設業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・重機が後退時に周囲を確認していない → 作業員との接触やはさまれ事故の危険 ・電動工具のコードが通路に垂れている → 足を引っかけて転倒するおそれ ・足場上での資材の仮置きが不安定 → 落下によって第三者に当たるリスク ・資材を手運びしているときに足元が見えていない → 躓いて転倒・負傷するおそれ |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・重機や人、工具・資材が混在する環境では、「見えていない」「気付いていない」ことが大きな事故を引き起こす ・一人の不注意が、現場全体の重大災害につながる |
| あなたならどうする(対策立案) | ・重機操作前の「合図者配置」と「後方確認」を徹底する ・電動工具やコードは整理整頓し、通路に出ないように管理する ・足場上では資材の仮置きを避け、安全な位置に保管する ・運搬時は前方確認を優先し、必要に応じて2人以上で作業する |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「声かけ・確認・合図を現場全体で徹底する」 ・「整理整頓・通路確保を基本行動とする」 ・「作業ごとの危険を常に予測し、動作前に考える習慣をつける」 を行動目標とする |
例文2.製造業

製造業では、多種多様な機械・設備を扱うため、巻き込み・切創・感電・火災・薬品の飛散など、機械的・化学的なリスクが常に存在します。
さらに、長時間労働による疲労や単調な作業環境による集中力の低下も、ヒューマンエラーのリスクを高める要因です。
【製造業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・機械の安全カバーを外したまま運転している → 回転部に手や衣類が巻き込まれる危険 ・加工物の取り付けが不十分な状態で作業開始 → 加工中に部品が飛散し、目や体に当たるおそれ ・清掃中に電源を切り忘れている → 誤作動で巻き込まれるリスク ・化学薬品を取り扱う際に手袋や保護メガネを未着用 → 皮膚障がいや目の損傷を引き起こすおそれ |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・「いつも大丈夫だから」という油断が、突発的な事故を引き起こす最大の要因 ・安全装置の不使用や保護具の軽視が、一瞬で重大事故につながる |
| あなたならどうする(対策立案) | ・始業前点検で、安全装置の有無と作動状況を確認する ・加工物の固定状態は、作業前に必ず再確認する ・清掃やメンテナンス時は、主電源をオフにして作業を行う ・薬品使用時は、SDS(安全データシート)を確認し、適切な保護具を着用する |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「安全装置を正しく使用し、慣れに頼らない作業を心がける」 ・「確認作業を省略せず、危険予知を毎日繰り返す」 ・「保護具は『最後の砦』と考え、必ず正しく装着する」 を行動目標とする |
例文3.物流業

物流業(倉庫・配送・構内搬送など)では、フォークリフトや台車などの搬送機器と人が混在する環境での作業が多く、接触・はさまれ・転倒などの事故が起こりやすい環境です。
高所作業や荷崩れ、荷扱いによる腰痛・手指の挟み込みなど、多様なリスクが潜んでいます。
【物流業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・フォークリフトが通路の角から急に出てくる → 歩行者と接触・はさまれの危険 ・荷物を高く積み上げたまま運搬している → 前方視界不良による衝突や転倒のおそれ ・重量物を一人で無理に持ち上げている → 腰痛や転倒によるけがのリスク ・棚の上段に積まれた荷物が不安定な状態 → 落下による直撃事故の危険 |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・人と物の動線が交錯する環境で、「見えない」「気付かない」ことが事故を招く ・荷物の安定性や姿勢の無理が、身体への負担や長期的な障がいにつながる |
| あなたならどうする(対策立案) | ・交差点や死角では一時停止を徹底する ・高積みを避け、視界を確保した状態で運搬する ・重量物は2人以上で持つか、ハンドリフトなどを使用する ・棚やパレットの積載状態を日常的に点検し、不安定な荷物は安定する場所に積み直す |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「人と機械の動線分離を徹底し、接触リスクを最小化する」 ・「荷物の安定と作業姿勢の適正を常に意識する」 ・「声かけ・確認・点検を『毎回・全員』で習慣化する」 を行動目標とする |
例文4.医療・福祉業

医療・福祉業では、転倒・誤薬・感染症・腰痛といった身体的・精神的双方の負担とリスクを常にともないます。
職員の「慣れ」や「多忙さ」からくる判断ミスや確認漏れが、重大な事故や医療過誤につながりかねません。
【医療・福祉業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・利用者の状態を確認せずに乗り移り作業を開始した → 体調急変やバランス崩れによる転倒の危険 ・床に水滴や尿が落ちたまま放置されている → 職員や利用者が滑って転倒するリスク ・複数の薬を並行して準備している → 他人の薬を誤って渡す誤薬のおそれ ・感染症の流行時に手指消毒やマスク着用が徹底されていない → 集団感染の発生リスク |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・利用者の命や身体に直結する作業が多いため、1つの判断ミスが重大事故を招く ・慣れや忙しさによる確認不足がリスクを高める |
| あなたならどうする(対策立案) | ・介助前に体調・表情・返答内容を確認し、無理な動作は避ける ・床の異常(濡れ・異物)に気付いたら即対応し、周囲にも声かけする ・薬は1人分ずつ確認しながら準備・投与し、ダブルチェック体制を徹底する ・感染対策マニュアルを常に確認し、職員同士で注意喚起を行う |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「『見て・聞いて・感じる』利用者の変化に気付く力を高める」 ・「『声かけ・手順確認・報告』の習慣を徹底する」 ・「『自分は大丈夫』の油断を捨て、チーム全体で安全を守る」 を行動目標とする |
例文5.飲食業

熱気、油、水が飛び交う飲食店の厨房は、包丁などの刃物や高温の調理器具が絶えず使用され、切り傷、火傷、転倒といった事故のリスクが常に潜んでいます。
特に、ピークタイムの混雑と焦りは従業員の注意力を削ぎ、日々の作業から生まれる「慣れ」や「ながら作業」が、火災や食中毒など、店の存続を揺るがすトラブルにつながることもあります。
【飲食業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・包丁を持ったまま振り向いて話しかけている → 誰かに接触して切創事故につながるおそれ ・コンロ周辺に布巾や紙などの可燃物が置かれている → 火が燃え移る火災の危険 ・床に油や水がこぼれたままになっている → 滑って転倒し、やけどや骨折のリスク ・同じ容器に複数のアレルゲンを扱っている → アレルギー事故による健康被害のおそれ |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・厨房内は熱・刃物・水・油・人が密集しており、一つの油断が多重事故を誘発する ・「急いでいる」「慣れている」という心理が事故の要因になる |
| あなたならどうする(対策立案) | ・刃物は使わないときはすぐに所定の位置へ戻す ・火の周囲は常に片付けて、可燃物は遠ざける ・床に液体がこぼれたら即拭き取り、滑り止めマットを敷く ・アレルゲン食材はラベル・器具を分けて管理し、二重確認を行う |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「刃物・火気・足元の安全確認を意識する」 ・「『慌てず・焦らず・安全に』を合言葉にチームで声をかけ合う」 ・「アレルゲン管理と衛生管理を最重要事項として共有する」 を行動目標とする |
例文6.小売業

小売業では、品出しやレジ対応など多岐にわたる作業が同時並行で行われることによる来店者との接触事故や、狭い売場での脚立作業・商品の落下事故などのリスクがあります。
慣れや忙しさからくる「注意不足」や「安全手順の軽視」などの行動が、従業員自身の転倒や労災にもつながりかねません。
【小売業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・脚立を固定せずに商品を上段に補充している → バランスを崩して転落する危険 ・棚に積まれた商品が不安定な状態 → 落下してお客様や従業員に当たる恐れ ・店内の床にこぼれた液体が放置されている → 滑って転倒するリスク ・バックヤードで段ボールを高く積み上げている → 崩れて下敷きになる危険 |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・接客エリアと作業エリアが同じ場所にあるため、作業者だけでなく来店客にも危険が及ぶ ・日常的な作業こそ事故に直結しやすく、確認を怠ったときに災害が発生する |
| あなたならどうする(対策立案) | ・脚立を使うときは必ず水平で安定した場所に設置し、声かけ確認を行う ・高い位置の陳列物は落下防止のため重さや置き方を工夫する ・床の汚れや液体はすぐに拭き取り、「清掃中」表示を設置する ・積み上げた荷物は高さ制限を設け、倒れないように間隔を空けて保管する |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「作業時は周囲の人の安全も意識する」 ・「転倒・落下・接触の三大事故を常に予測して行動する」 ・「基本動作を徹底し、いつもどおりを見直す習慣を持つ」 を行動目標とする |
例文7.清掃業

清掃業では、水・洗剤・電気機器などを扱うため、転倒・感電・化学薬品による肌荒れや呼吸器トラブルのリスクが考えられます。
作業中に施設の利用者や通行人と接触してしまうことで事故につながったり、使用中の薬品が原因で思わぬ二次災害を引き起こしたりするおそれもあるため、十分な配慮が必要です。
【清掃業の危険予知活動例文】
| どんな危険が潜んでいるか(現状把握) | ・清掃中の床に「作業中」の表示がない → 通行人が滑って転倒する危険 ・脚立をぐらついたまま使用して窓拭きをしている → バランスを崩して転落するリスク ・電源を入れたまま掃除機の分解清掃を行っている → 感電や機器の誤作動によるけがのおそれ ・強い洗剤を換気の悪い場所で使用している → 吸い込みによる体調不良や目・喉への刺激の危険 |
|---|---|
| これが危険のポイントだ(本質追求) | ・作業環境と通行環境が重なる現場では、「第三者への影響」も注意しなければならない ・高所・電気・薬品といった複合的なリスク要素が常に存在している |
| あなたならどうする(対策立案) | ・床清掃中は「作業中」のような標識を必ず設置する ・脚立は安定した場所で使用し、天板に乗らない ・電源を切ってから掃除機の内部点検や手入れを行う ・薬剤は換気をしながら使用し、必要に応じてマスクや手袋を着用する |
| 私たちはこうする(目標設定) | ・「自分の安全+周囲の人への配慮を意識して行動する」 ・「使用前点検と保護具の装着を必ず実施する」 ・「ながら作業や慣れを排除し、作業ごとにリスクを確認する」 を行動目標とする |
危険予知活動(KY活動)のマンネリ化を防ぎ、効果を高めるポイント

本章では、危険予知活動(KY活動)のマンネリ化を防ぎ、効果を高めるポイントについて解説します。
ポイント1.ヒヤリハットの事例やリスクアセスメントの結果を活用する
危険予知活動(KY活動)のマンネリ化を防ぎ、効果を高めるためには、ヒヤリハット事例やリスクアセスメントの結果を活用することが重要です。
主なポイントは、次のとおりです。
| ヒヤリハット事例の具体的活用 | 現場で起きた「ヒヤリとした」「ハッとした」事例を危険予知活動の題材にする |
|---|---|
| リスクアセスメントデータの反映 | 事前に実施したリスクアセスメントの結果(危険度ランクや優先対策)を危険予知活動に反映させる |
| 実施方法の工夫 | 次のように実施方法を工夫する ・事例の可視化 ヒヤリハット事例を写真やイラストで提示し、危険をイメージしやすくする ・ロールプレイ 実際の事例を再現し、作業員が「自分ならどうするか」を体験できるようにする ・データ分析 過去のヒヤリハットや災害統計から傾向を分析し、重点対策を明確にする |
| 継続的な更新 | ヒヤリハット事例やリスクアセスメント結果を定期的に見直し、季節や作業内容に応じて危険予知活動のテーマを更新していく |
危険予知活動をマンネリ化させないポイントは「現場の声を拾い、データに基づいた議論を習慣化すること」です。
現場の声に応じて工夫を重ねることにより、危険予知活動を「形式的なチェックリスト」から「実践的な危険回避の行動」へ発展させていきましょう。
なお、労働災害の約96%に含まれるという「不安全行動」について要因や事例を下記の記事で紹介していますので、併せてご覧ください。
ポイント2.目的を再確認し、現場の参加意欲を高める工夫をする
危険予知活動の目的は、作業現場に潜む危険をあらかじめ見つけ出し、労働災害を未然に防ぐことです。
この目的を現場で繰り返し共有し、参加者一人ひとりが「自分ごと」として意識することで、参加意欲の向上が期待できます。
具体的には、次のような工夫が有効です。
- なぜ危険予知活動が重要なのかを、定期的に共有する
- 危険予知活動のテーマ設定で、参加意欲を引き出す
- 進め方に変化をつけ、全員参加型の危険予知活動を目指す
危険予知活動は「やらされるもの」から「現場の安全を守るために欠かせない習慣」へと変化させ、組織全体の安全文化を醸成していきましょう。
ポイント3. 「報告しやすい・意見を言いやすい」環境づくりを徹底する
危険予知活動の場では、誰もが気軽に危険や改善点を報告・発言できる雰囲気づくりが大切です。
そのためには、上司やリーダーが積極的に意見を求め、どんな意見も否定せず受け止める姿勢を示しましょう。
小さな気づきや発言、指摘であっても、「よく気づいてくれたね!」「ありがとう!」と心から称賛し、積極的に言葉にしましょう。 言葉にすることで、「自分の意見が尊重される」「発言しても大丈夫だ」という安心感が現場に広がり、一人ひとりの安全意識が自然と高まります。
【危険予知活動で注目】防犯カメラ活用で「見える化」する安全管理と現場DX

近年、危険予知活動(KY活動)においてカメラの活用が注目されています。本章では、その理由を2つの視点と1つの事例から解説します。
1.なぜ危険予知活動に防犯カメラが役立つのか?
防犯カメラは、現場の状況把握や危険行動の可視化・事故原因の究明などのあらゆる観点から、危険予知活動(KY活動)に役に立つといえます。
【危険予知活動に防犯カメラが役立つ主な理由】
| 現場の状況把握とリアルタイム監視 | ・現場全体や危険なエリアをリアルタイムで監視しやすくなる ・「死角」や「見落とし」の軽減につながる |
|---|---|
| 危険行動やヒヤリハットの可視化 | ・実際に起きたヒヤリハットや危険な行動を映像で記録し、危険予知活動の題材として活用できるようになる ・映像を使えば、抽象的な説明よりも具体的なイメージを持ちやすく、参加者の理解や危機意識を高められる |
| 事故原因の究明と再発防止 | ・万が一事故が発生した場合、防犯カメラの映像が原因究明や再発防止のための貴重な証拠となる ・映像から作業手順や危険な行動を分析し、今後の危険予知活動や安全対策に活かせる |
| 作業員の安全意識向上 | ・カメラが設置されていることで、作業員は「常に見られている」という意識が働き、安全意識の向上にもつながる |
このように、防犯カメラは危険予知活動の効果を高めるための「目」となり、現場の安全を多方面からサポートするのです。
2.危険予知活動に役立つ「G-cam」「G-POKE」
危険予知活動に防犯カメラを活用したい場合は、株式会社MIYOSHIが提供するカンタン監視カメラ「G-cam」や小型ボディカメラ「G-POKE」がおすすめです。
初期費用0円、月額9,800円からレンタルが可能で、初期コストを抑えて導入できます。

G-cam・G-POKEが危険予知活動におすすめな理由は、下記のとおりです。
- 【G-cam】

- ・レンズ横回転最大350°縦回転最大90°で現場全体を広範囲・高画質で監視でき、死角を減らして作業中の危険行動やヒヤリハットを映像で記録できる
- ・クラウド保存や遠隔監視機能もあり、本社や関係者がリアルタイムで現場状況を把握し、危険予知活動の題材や安全対策の検討に活用できる
- 【G-POKE】

- ・作業員が装着して作業中の映像を記録でき、固定式カメラでは撮影が難しい手元や死角も補完できる
- ・ライブ映像通話やリアルタイム共有も可能で、遠隔地からも現場の状況を把握し、安全指導や危険予知の議論に役立つ
G-cam・G-POKEともに難しい設定は一切不要・モバイルSIMが内蔵されているので届いたその日にすぐに監視をスタートできます。
初期費用0円、月額9,800円からレンタル利用できるため、導入のハードルが低く、工期の短い現場でも手軽に取り入れられるのが魅力です。
低コストで防犯カメラを活用し現場の危険予知活動につなげたい方は、下記のボタンより資料をダウンロードしてみてください。
\G-cam・G-POKEで死角を減らし、作業員の安全を守る! /
3.【事例紹介】カメラ導入でここまで変わる!危険予知活動の進化

株式会社MIYOSHIのカンタン監視カメラ「G-cam」を導入したことで、危険予知活動につながっている企業様の事例を紹介します。
清水建設株式会社様は、建築・土木・海外建設を主軸としつつ、不動産開発、エンジニアリング、グリーンエネルギー開発など多岐にわたる事業を展開する総合建設会社です。事務所と現場は離れており、移動時間が課題となっていました。
そこで、タワークレーンに2台の「G-cam」を設置し、現場全体を俯瞰できる環境を構築。その結果、現場に足を運ばなくても危険な行動や状況をリアルタイムで確認できるようになり、危険予知活動にも活用されています。さらに、監視カメラで気になる点を発見した際には、職長への連絡や現地確認を即座に行えるようになり、現場管理の迅速化にもつながっています。
>>>事例の詳細はこちら|導入いただいたお客様のお声【清水建設株式会社様】
「使える例文」で危険予知活動(KY活動)は変わる!今日から始める安全意識改革

危険予知活動(KY活動)を現場で定着させていくには、形式的な実施で終わらせず、実効性のある運用が欠かせません。
本記事で紹介した「使える例文」やポイントを参考にしながら、日々のヒヤリハット事例の共有や危険箇所を見える化するなどの工夫を取り入れて、危険予知活動を活性化していきましょう。
危険予知活動を効率よく進めていくためには、防犯カメラの活用も有効です。人の目が届きにくい場所の死角をなくすだけでなく、映像という客観的な記録をもとに、より具体的な危険予知の議論ができます。また、「常に見られている」と作業員が意識することで、安全意識の向上も期待できます。
株式会社MIYOSHIが提供するカンタン監視カメラ「G-cam」や小型ボディカメラ「G-POKE」は、1週間の無料レンタルを実施中です。使用感を確かめたい、どのようなカメラなのか詳細を知りたい方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
\モバイルSIM内蔵・ネットワークの設定不要で専門知識は不要!/